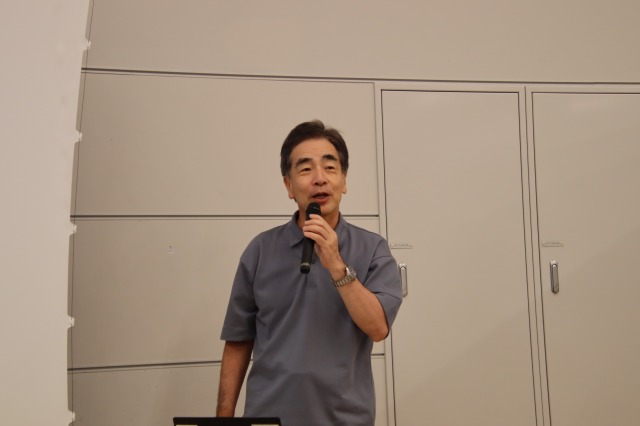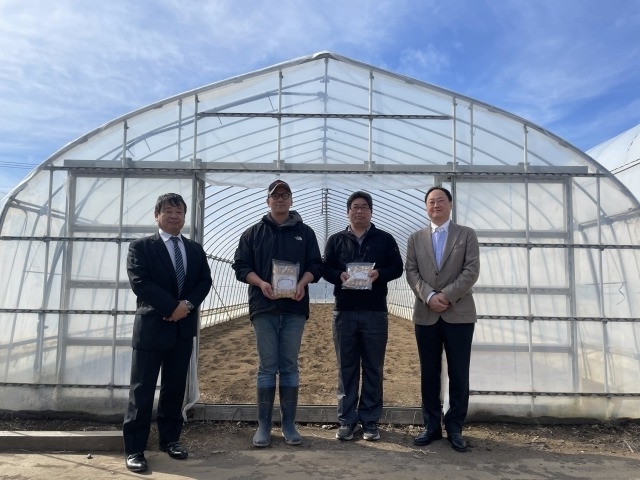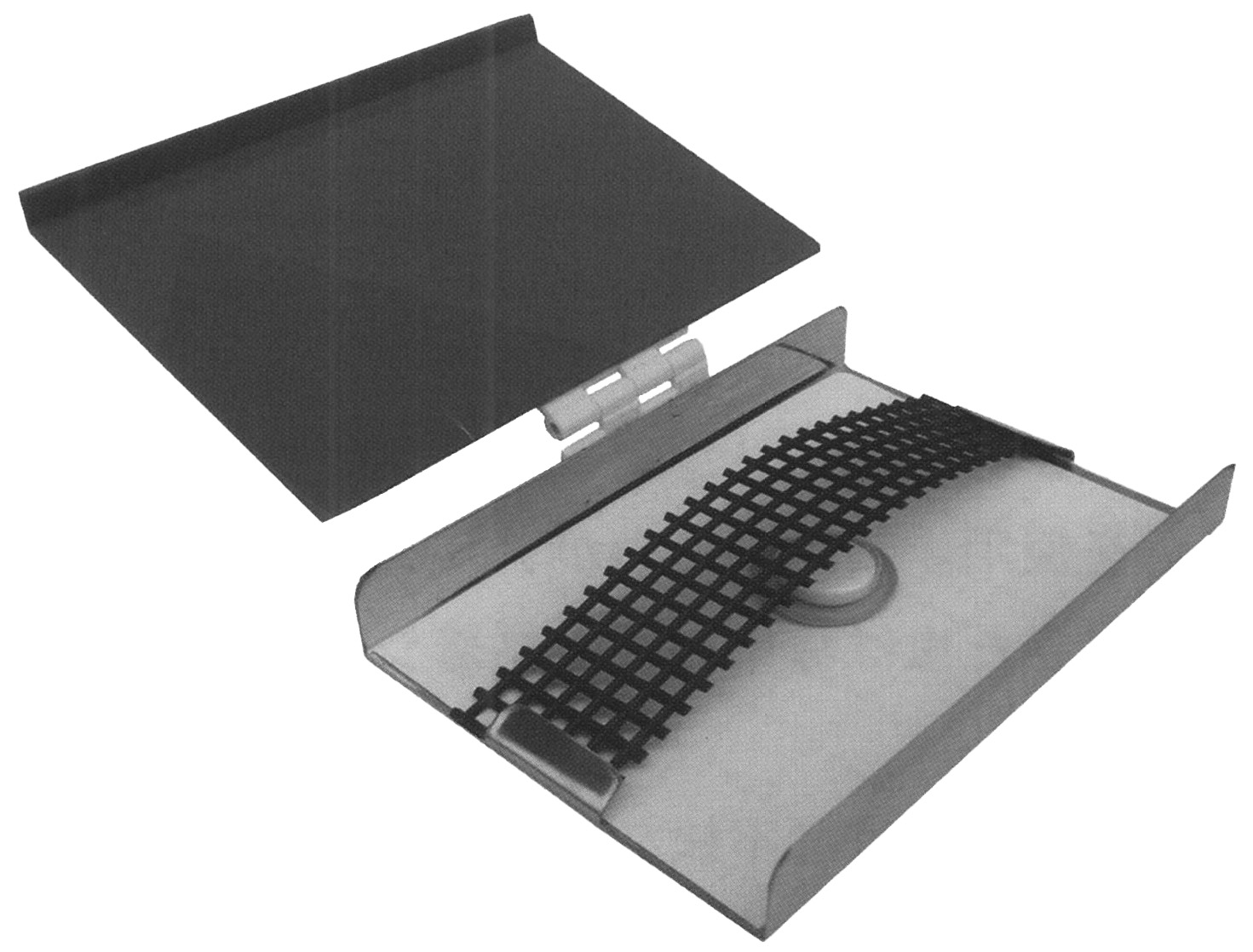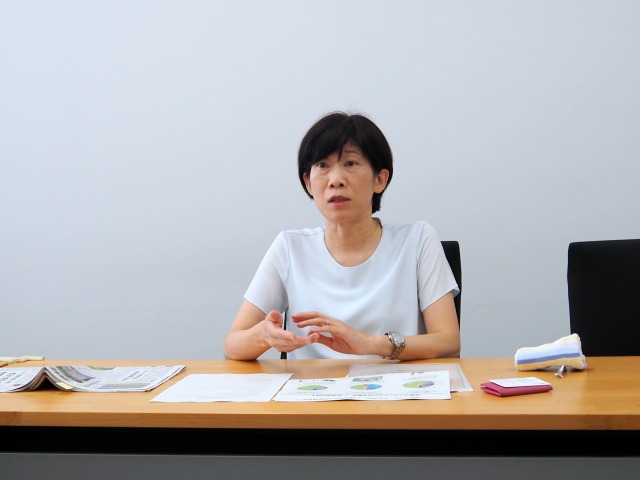水稲の収量安定と品質向上に貢献するバイオスティミュラント資材「エヌキャッチ」と「ヒートインパクト」
水稲生産において、収量の安定化と品質向上は重要な課題である。近年は化学肥料の価格高騰や環境負荷低減の要請に加え、気候変動による高温障害や干ばつなど、栽培環境はますます厳しくなっている。こうした状況で注目されているのが、作物の潜在能力を引き出すバイオスティミュラント資材である。本稿では、ファイトクロームが運営する「環境ストレス研究会」の実証で明らかになった「エヌキャッチ」と「ヒートインパクト」の効果...



.png)