林野庁研究指導課・安髙課長に聞く 安全性確保が最重要 林業イノベーションを展開
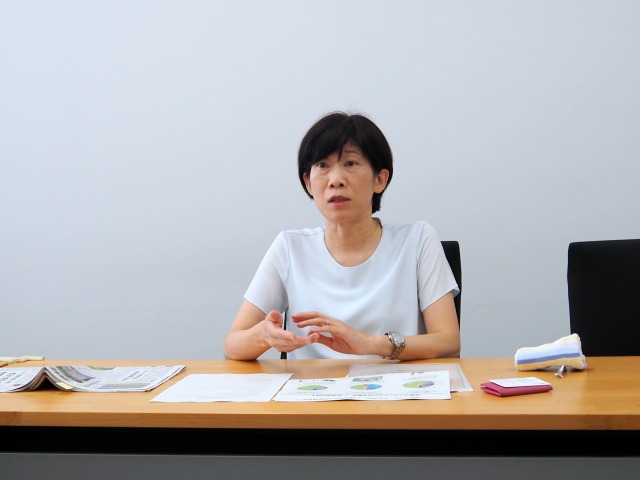
わが国の林業を巡っては、戦後植林された人工林が利用期を迎える一方、わが国全体の人口減なども影響し、従事者の減少が続くなど課題も多い。そうしたなかで、省力・効率化につながる林業機械への期待はますます高まっている。
林業を巡る現状と課題、そして林業機械を巡る動向について、林野庁森林整備部研究指導課の安髙志穂課長に話を聞いた。
――改めて林業現場を取り巻く課題は。
「大きく3つある。一つ目は安全性、二つ目は生産性、三つ目は収益性。なかでも一番の課題と捉えているのが安全性の向上。林業における死傷者数は長期的には減少傾向にあるものの、死傷年千人率でみると、全産業平均の10倍と高くなっており、さらなる労働災害発生率の改善が喫緊の課題だ。林野庁では、死傷年千人率について、令和12年までに令和2年と比較して半減(12・7人)を目指す目標を設定。その実現に向けては、近年開発が進む林業機械の『遠隔操作化』『自動化』はなくてはならないと考えている」
「林業における死亡事故で最も多い作業が伐倒。伐倒現場から離れて作業できる遠隔操作化・自動化は安全性を大幅に高められると認識している」
――遠隔操作化、自動化に向けた林野庁の具体的な取組は。
「現在、技術開発や実証の支援を行っており、令和7年度概算要求では、『林業デジタル・イノベーション総合対策』のうち、『戦略的技術開発・実証事業』について前年度予算額から2000万円増の9000万円を要求している。支援対象を『素材生産分野』『造林分野』と明確化するとともに『通信』についての開発・実証を追加した。この予算確保に向けて尽力したい」
――遠隔操作化・自動化の社会実装に向けて必要なことは。
「機械開発の推進はもちろんだが、施業体系の検討も必要。例えば、下刈りの際に機械が入ることを前提とした苗木の植栽間隔にするといったことだ。遠隔操作式下刈機械が実用化されるなど今後遠隔操作での施業を普及させるためにも施業体系の検討も視野に入れていきたい」
「加えて、林業機械が自動運転や遠隔操作を行っている最中は機械から作業者が離れるので、機械の周囲の安全確保など新たな安全対策が必要。林野庁は今年7月、『林業機械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会』を設置。安全対策のガイドラインの検討を始めた。まずはガイドラインを適用する者、使用上の条件など安全確保の基本的事項を今年度中にとりまとめることを想定している。下刈、伐倒、集材等各作業の内容や遠隔操作・自動化の進展レベルも異なることから、今年度中に全ての林業機械を網羅することは出来ないが、今後の技術開発の進展状況などを踏まえて、継続してガイドラインの見直しを行っていきたいと考えている」
――生産性・収益性の向上に向けては。
「林業の安全性を確保したうえで労働生産性及び林業経営の収益性の向上の実現を目指して、林野庁では前述の林業機械の自動化・遠隔操作化に加え、ICT等を活用した資源管理、エリートツリーの植栽などの新技術の開発、普及を図る『林業イノベーション』を推進している」
「成長の早いエリートツリーは下刈りコストの縮減や収穫期間の短縮など、生産性と収益性の向上に加え、花粉量の減少にもつながる重要な存在。林業用苗木に占めるエリートツリーの割合を2030年までに3割にするとの目標を掲げている。2022年度実績で約1割だが順調に増加しているところだ。更に生産量を増やし、植栽を進めていきたい」
「加えて重要なのが、新たな木材需要の確保。林野庁では、『丸太オンリーからの脱却』を掲げ、木材の新たな付加価値創出に向け、『マテリアル利用』の開発を積極的に推進している。その一例が改質リグニンだ。これまで森林総研とメーカーが共同で用途開発・試作品製造を進めてきた。この成果が実を結び、いよいよ社会実装に向けた大規模製造技術の実証が始まろうとしている。今後は市場へ訴求するために、優位性のある用途開発、環境適合性の評価等を進める必要がある」
「もう一つユニークな取組として紹介したいのが『木の酒』だ。木材を化学処理することなく、細かく砕いて発酵させる。スギやシラカンバ、ミズナラなど原料とした樹種に応じた特徴的な香りを持っており、比べてみるのも楽しいと思う。開発した森林総研では、事業化を希望する企業を対象に研修を実施し、技術移転を進めているところだ」
――遠隔操作化・自動化以外のスマート林業について。
「ドローンや航空機による資源調査はある程度広がってきてはいるが『浸透している』とまでは言い難い。地域一体で、森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用すべく、『デジタル林業戦略拠点構築推進事業』において全国3地域(北海道、静岡、鳥取)で実証を進めている。なかでも、川上から川下まで上手く繋げているのが鳥取県の取組だ。平成14年度から運用されている『県産材産地証明制度』が土台としてあることがポイントだ。川上から川下の複数の関係者を巻き込んだデジタル化と言うは易しだが、実現は難しい。デジタル化以前に関係者間の『合意形成』が極めて重要」
「本事業での支援は、令和5年度から3年間を予定。各地域の成果をしっかりと取りまとめ、8年度からは取組の横展開を進めていきたい」
――森林・林業・環境機械展示実演会に向けて。
「林業は山の奥で施業しており、なかなか見ることができない。しかし、機械展示実演会では、『こんな大きい機械を使っているんだ』『こんな作業をしているんだ』というように林業に接して頂ける絶好の機会。素材生産業者や森林組合など林業関係者の方々はもちろんのこと、ご家族連れや学生の方、異分野企業など幅広い方々に来場頂き、林業の魅力を感じていただける場となることを期待している」。
林業を巡る現状と課題、そして林業機械を巡る動向について、林野庁森林整備部研究指導課の安髙志穂課長に話を聞いた。
――改めて林業現場を取り巻く課題は。
「大きく3つある。一つ目は安全性、二つ目は生産性、三つ目は収益性。なかでも一番の課題と捉えているのが安全性の向上。林業における死傷者数は長期的には減少傾向にあるものの、死傷年千人率でみると、全産業平均の10倍と高くなっており、さらなる労働災害発生率の改善が喫緊の課題だ。林野庁では、死傷年千人率について、令和12年までに令和2年と比較して半減(12・7人)を目指す目標を設定。その実現に向けては、近年開発が進む林業機械の『遠隔操作化』『自動化』はなくてはならないと考えている」
「林業における死亡事故で最も多い作業が伐倒。伐倒現場から離れて作業できる遠隔操作化・自動化は安全性を大幅に高められると認識している」
――遠隔操作化、自動化に向けた林野庁の具体的な取組は。
「現在、技術開発や実証の支援を行っており、令和7年度概算要求では、『林業デジタル・イノベーション総合対策』のうち、『戦略的技術開発・実証事業』について前年度予算額から2000万円増の9000万円を要求している。支援対象を『素材生産分野』『造林分野』と明確化するとともに『通信』についての開発・実証を追加した。この予算確保に向けて尽力したい」
――遠隔操作化・自動化の社会実装に向けて必要なことは。
「機械開発の推進はもちろんだが、施業体系の検討も必要。例えば、下刈りの際に機械が入ることを前提とした苗木の植栽間隔にするといったことだ。遠隔操作式下刈機械が実用化されるなど今後遠隔操作での施業を普及させるためにも施業体系の検討も視野に入れていきたい」
「加えて、林業機械が自動運転や遠隔操作を行っている最中は機械から作業者が離れるので、機械の周囲の安全確保など新たな安全対策が必要。林野庁は今年7月、『林業機械の自動運転・遠隔操作に関する安全対策検討会』を設置。安全対策のガイドラインの検討を始めた。まずはガイドラインを適用する者、使用上の条件など安全確保の基本的事項を今年度中にとりまとめることを想定している。下刈、伐倒、集材等各作業の内容や遠隔操作・自動化の進展レベルも異なることから、今年度中に全ての林業機械を網羅することは出来ないが、今後の技術開発の進展状況などを踏まえて、継続してガイドラインの見直しを行っていきたいと考えている」
――生産性・収益性の向上に向けては。
「林業の安全性を確保したうえで労働生産性及び林業経営の収益性の向上の実現を目指して、林野庁では前述の林業機械の自動化・遠隔操作化に加え、ICT等を活用した資源管理、エリートツリーの植栽などの新技術の開発、普及を図る『林業イノベーション』を推進している」
「成長の早いエリートツリーは下刈りコストの縮減や収穫期間の短縮など、生産性と収益性の向上に加え、花粉量の減少にもつながる重要な存在。林業用苗木に占めるエリートツリーの割合を2030年までに3割にするとの目標を掲げている。2022年度実績で約1割だが順調に増加しているところだ。更に生産量を増やし、植栽を進めていきたい」
「加えて重要なのが、新たな木材需要の確保。林野庁では、『丸太オンリーからの脱却』を掲げ、木材の新たな付加価値創出に向け、『マテリアル利用』の開発を積極的に推進している。その一例が改質リグニンだ。これまで森林総研とメーカーが共同で用途開発・試作品製造を進めてきた。この成果が実を結び、いよいよ社会実装に向けた大規模製造技術の実証が始まろうとしている。今後は市場へ訴求するために、優位性のある用途開発、環境適合性の評価等を進める必要がある」
「もう一つユニークな取組として紹介したいのが『木の酒』だ。木材を化学処理することなく、細かく砕いて発酵させる。スギやシラカンバ、ミズナラなど原料とした樹種に応じた特徴的な香りを持っており、比べてみるのも楽しいと思う。開発した森林総研では、事業化を希望する企業を対象に研修を実施し、技術移転を進めているところだ」
――遠隔操作化・自動化以外のスマート林業について。
「ドローンや航空機による資源調査はある程度広がってきてはいるが『浸透している』とまでは言い難い。地域一体で、森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用すべく、『デジタル林業戦略拠点構築推進事業』において全国3地域(北海道、静岡、鳥取)で実証を進めている。なかでも、川上から川下まで上手く繋げているのが鳥取県の取組だ。平成14年度から運用されている『県産材産地証明制度』が土台としてあることがポイントだ。川上から川下の複数の関係者を巻き込んだデジタル化と言うは易しだが、実現は難しい。デジタル化以前に関係者間の『合意形成』が極めて重要」
「本事業での支援は、令和5年度から3年間を予定。各地域の成果をしっかりと取りまとめ、8年度からは取組の横展開を進めていきたい」
――森林・林業・環境機械展示実演会に向けて。
「林業は山の奥で施業しており、なかなか見ることができない。しかし、機械展示実演会では、『こんな大きい機械を使っているんだ』『こんな作業をしているんだ』というように林業に接して頂ける絶好の機会。素材生産業者や森林組合など林業関係者の方々はもちろんのこと、ご家族連れや学生の方、異分野企業など幅広い方々に来場頂き、林業の魅力を感じていただける場となることを期待している」。

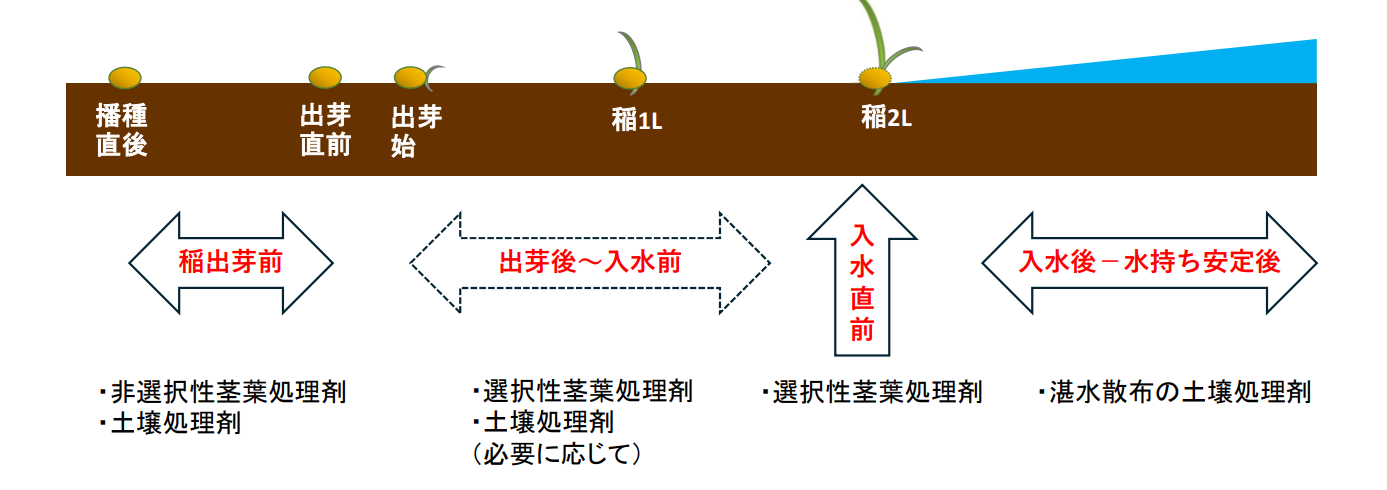
 (1).JPG)





