新春特別インタビュー 渡邊毅事務次官に聞く

持続性の確保目指す 全生産者がスマ農活用する社会へ
昨年は、四半世紀ぶりに食料・農業・農村基本法の改正が行われ、新たな時代の農政に一歩踏み出した。一方、農業を巡っては厳しい情勢に置かれている。否応なく進む担い手の減少・高齢化、高止まりを続ける生産資材等の価格とそれを十分に反映しきれてない農産物価格など。転換期にある今はまさにこうした課題を解決し、反転攻勢をしかける絶好の機会だ。今回、新春特別インタビューとして、農林水産省の渡邊毅事務次官に今後の農政の方向性などを聞いた。
――昨年、25年ぶりに 食料・農業・農村基本 法が改正されました。 改めて前基本法下での わが国農業を振り返っ て頂けますか。
「この25年で世界情勢は大きく変わった。(前基本法が成立した)1999年頃は、日本に経済力があり、世界的にも穀物在庫に比較的余裕があったため、日本は、食料を十分調達できる立場にいて、プライスリーダーとなっていた。翻って現在は、世界人口が急激に増加し、食料をみんなで取り合うような状況になってきている。加えて、中国の経済力が上がり、日本が買い負けするような状況も起こっている。もう一点挙げられるのは気候変動。これについては、世界的な課題として取り組まなければならない」
「こうした大きな変化に加え、10年、20年先の将来を見据えた時何をすべきか、という点も重要になる。今後、世界的には人口が益々増える見込みの一方、日本の人口は、2050年には2000万人ほど減少し、約1億人にまで減ると見込まれる。基幹的農業従事者は、今までの倍のスピードでいなくなる。農業生産面でも担い手の減少に加え、国内需要の減少という課題も生まれる」
――そうした課題のなか、今回の基本法改正のポイントは。
「主に①食料安全保障の確保②環境対応③人口減対応の3点が上げられる。これらのいずれにも共通するのは『持続性の確保』だ」
「食料安保に関しては、わが国の農地は、 今の食生活を支えるために必要な面積の3分の1しかないという状況下にあって、食料自給率を100%にまで引き上げるのは現実的ではない。しかし、少しでも国内の生産力を高める努力をしなければならない。このため、輸入依存度の高い麦・大豆、飼料作物の生産を強化していく。加えて、海外依存度が高い肥料などの生産資材についても、輸入先の変更や国内で活用できる資源の活用を進めていく。例えばリンは相当程度中国から輸入していたが、モロッコからの輸入を増やした。また、堆肥や下水汚泥の活用を図るなど、構造転換を行っていく」
「環境対応については、基本法に先駆け『みどりの食料システム戦略』を策定。化学肥料や化学農薬の使用量低減やCO2ゼロエミッション化など様々な目標を定めており、それらを達成するため、環境に負荷を与えない農業のやり方を実装していくことを基本法に明記した」
「人口減対応については、生産性の向上が必須となる。スマート農業など新しい技術を取り入れ、少ない人間でも効率的に農業ができるようにするとともに、スマート農業技術導入に必要な基盤整備、 農地の集積・集約を進めるなどを通じて生産性を向上させつつ付加価値向上も実現していく。更にその生産を支える農村を維持するためにも農道や水路の保全、(スマート農業にも必要だが)通信環境の整備など生活の利便性を確保することも盛り込んでいる」
――現在、検討中の食料・農業・農村基本計画はどのようなものになるのでしょうか。
「基本法はあくまで理念法であるが、まずは先の通常国会で、その実現のため、農地法や農振法の改正、食料供給困難事態対策法などで一定程度手当をした。そうした点以外の、これまで基本法をつくるうえで議論されたものの、具体化すべき施策として残っている宿題の回答を出すという方向で検討している」
――今回の基本法改正においては、様々な関連法案が成立、施行されています。なかでも、基本法改正のポイントとして指摘されたスマート農業技術については、昨年10月に所謂「スマート農業技 術活用促進法」が施行されました。その狙いや今後の期待は。
「今後20年ぐらいを見通すと、基幹的農業従事者は今の約4分の1にまで減少すると予想される。すなわち、平均で今の4倍耕作してもらわないと今の生産を維持できないということだ。だからこそ、経営を拡大できるところは、少ない人間でも効率的に営農するため、スマート農業が必要になる。それを後押しするのが今回の『スマート農業技術活用促進法』だ。同法では、単に機械の実装・普及を進めるだけでなく、機械に合わせた生産の仕方に変えなければならないところもある。それらを積極的に進めていく方々に、税制や金融面での支援をすることを位置づけている」
「ただし、スマート農業技術は大規模経営体だけの話ではない。先程述べたように、基幹的農業従事者が4分の1にまで減少するなかで、最先端の担い手だけでなく、全国津々浦々、すべての生産者がスマート農業を活用して生産性を上げていかなければ今の生産能力や農業の生産基盤を維持できない。農水省としては、そうした社会が来ることを目指し支援していく」
――農業を巡る重要な 課題の一つが「適正な 価格形成」ですが、現 在法制化に向けた検討 も進められています。 現状をどのように認識 しどのような法律とな るのでしょうか。
「価格については、食料の供給という点で考えた時、生産者だけでなく、加工や流通、小売など多様なプレーヤーが関与して成り立っている。生産者だけでなく、そうした食料システム全体の関係者がそれぞれの利益を確保しなければうまく流れない。だからこそ負担を分かち合う、誰かにしわ寄せが来ないようにすることが非常に重要だ。そうした世界を構築することが新たな法律の目指すところ」
「その実現のために必要なのがそれぞれの段階でどれだけコストがかかっているかを把握すること。『合理化の努力はしているが、これだけ上がったのだから、これくらいの価格上乗せをお願いしたい』と交渉できるようまずコストをしっかり把握して明確化する。そして、それを考慮した取引を実現していくというステップが必要だ。今回の法律では、それらを実現できる環境をつくるため、売り手と買い手に、やるべきことをやらなければ国が指導するという方向性でまとめたいと考えている。また、今回の法律外ではあるが、価格転嫁のためには、消費者の賃金が上がっていくことも必要だ。こちらについては、政府全体で後押ししていく」
――より効率化・省人 ・省力化が求められる なか、農業機械および それを供給する販売店 をはじめとした農機業 界に期待することは。
「生産性向上において人がやっていた作業を機械に置き換えるということは非常に重要。土地利用型ではある程度機械が入っていると思うが、果樹や野菜などの園芸作物を中心に機械化がまだ進んでないところもある。それらについては、国でも音頭を取って、スマート農業技術も使いながら、開発研究を進めていく。そうした機械の現場実装を進めるため、業界の方々とも連携していかねばならないと考えている。その際には、機械を所有するだけでなく、利用という観点から、サービス事業体の活用といった面も進めていく必要がある。そうした事業体へのハード・ソフトの提供、更にはメーカーさんや販売店さんなどが自らサービス事業体としての役割を果たす、ということも期待している。また、気候変動との関係では機械の電動化や水素化などGXを後押ししていくので、そうした機械の開発にご協力いただきたい」
「さらに、農業分野は他産業と比べ事故で亡くなる方の比率が高い。安全確保については、使い方も含め、機械で予防できる部分も多々あると思うので、業界一体となって取組の強化を進めてほしい」。

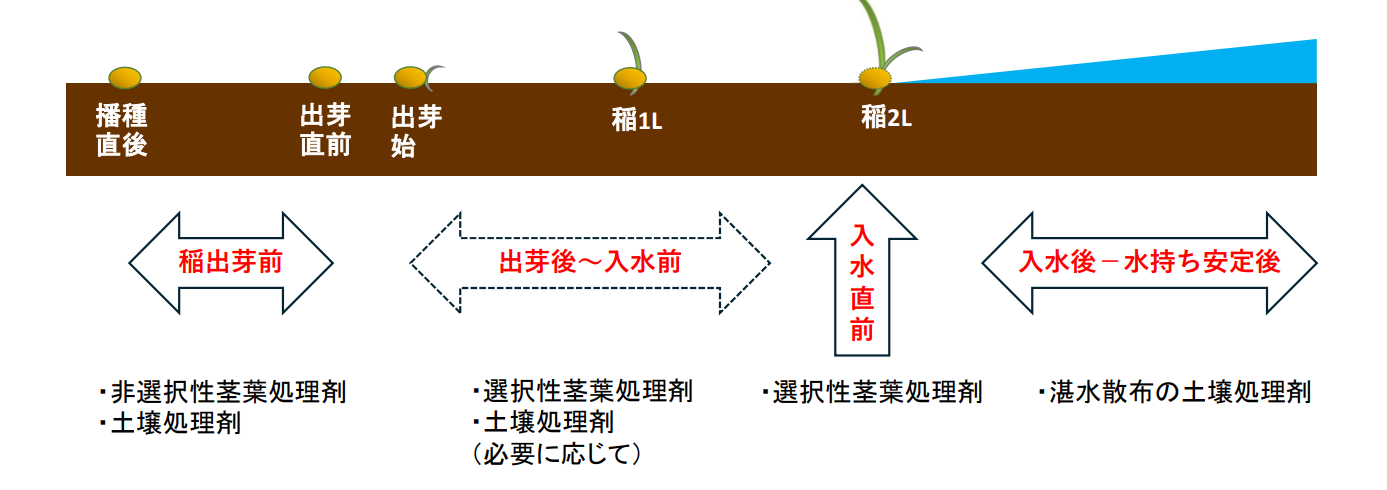
 (1).JPG)




