ヤンマーアグリグローバル大会 持続可能な農業・社会 〝不可欠なパートナー〟へ
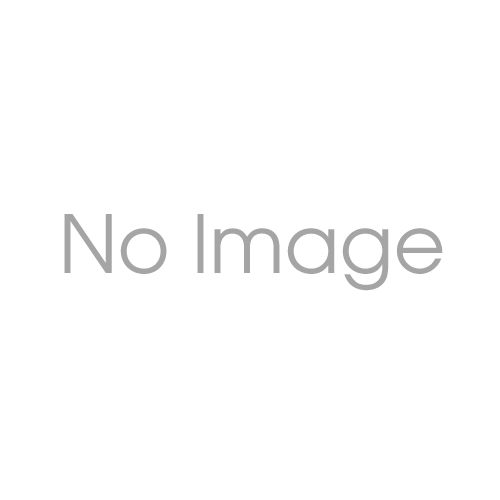
持続可能な農業・社会 〝不可欠なパートナー〟へ
2025年ヤンマーアグリグローバル大会は、大画面に、ギタリスト・MIYAVIさんが天気予報の曲として多くの人に馴染まれてきた「ヤン坊マー坊の歌」をアレンジした楽曲「Find A Way」を演奏するのをバックに、未来に向かって戸惑いながらも挑戦しようとする世界各国の若者、またその背中をそっと押す人、やがて、スキップしたり、ダンスしたり、飛んだり跳ねたり、手を叩きながら、若者達の輪は合流して大きくなり、前に進み続けていくという映像をつないで、前進しようとする若者たちのパワーが凝縮されたムービーで幕を開けた。桜の花びらが舞い、まさにヤンマーの目指す〝HANASAKA〟の精神を象徴していた。
その後、ヤンマーホールディングスの山本哲也代表取締役COOが登壇。「本大会は、ヤンマーを支えてくださるパートナーの皆さまへの感謝をお伝えする場として開催し、今年で49回目を迎えました。これも皆様のご支援とご協力の賜物です」と感謝の意を表し、「挑戦を支えるのは、ヤンマーの創業以来変わらぬDNAであり、先ほどのビデオにも象徴される〝HANASAKA〟の価値観です。農業の未来をワクワクできるものに変えていくため、共にチャレンジして参りましょう」と呼びかけた(別掲)。
次に、ヤンマーホールディングスの長屋明浩取締役CBOが挨拶。長屋取締役は、昨年11月に、東京・八重洲のヤンマー東京ビルのハナサカスクエアで開催したヤンマーの未来ビジョンを示した『みらいのけしき展』と同展で発表したコンセプトモデルを統括した人であり、ヤンマーのブランディングの責任者だ。挨拶では、ヤンマーの未来に向けた〝ありたき姿〟などを軸に話をした。その中でヤンマーのデザインフィロソフィーは「本質デザイン」であり、デザインの方向性は「柔和剛健」としたこと、これには、壊れにくく信頼性の高いプロダクトと人に優しいことがポイントとなると語った、また、それを視覚化したのが今回ロビーに展示したコンセプトモデルであると説明した(別掲)。今の時代に進化した新ヤン坊マー坊も登場。これからも〝人〟が中心のヤンマーであることを印象付けた。
このヤン坊マー坊はロビー展示のコンセプトモデルの前にも休憩時間に登場。来場者との記念撮影にも応じて、場を盛り上げた。
長屋取締役に続いて、ヤンマーアグリの所司ケマル代表取締役社長が挨拶。日頃のヤンマーの推進活動への協力とグローバル大会へ参加に対し感謝の意を表し、続いて「アグリ事業の取組み」について説明した。「不確実性がさらに高まる世界。これはまさに未知の領域だ。未知は不安なものである一方で可能性でもある。新たな取組みで、未知の可能性を応援し、みんなで未来をワクワクできるものに変えていこう。それがヤンマーの創業当時から受け継がれるHANASAKAの精神だ」と檄を飛ばし、〝新たな取組み〟を説明した(別掲)。
続いて国内外の事例紹介。始めに、広島県の迫農機商会の迫祐次氏と迫洋志氏。迫農機商会は、地域社会と一体になりながら、お客様の困りごとを丁寧に解決、〝お客様の身になって考え抜く〟ことが、新たなビジネスの循環が生んでいるという(別掲)。また、次の事例紹介はヤンマートルコマシナリー社だったが、同社は歴史の浅い会社でありながら、着実にトルコ国内でのシェアを拡大している。コーディネーターのアリ・オズポラット氏が更なる事業拡大に向けたチャレンジについて発表した。
その後、ヤンマーホールディングス奥山博史取締役CDOが、ヤンマーのデジタルについての考え方とデジタルで真に目指すこと、ヤンマーのデジタル戦略について講演した。奥山取締役は、1998年住友商事入社。化学品部門でマーケティングや営業を担当。その後、数社で戦略立案・実行、ガバナンス、マーケティングの要職を担当後、2015年にヤンマーホールディングスに入社、経営企画部長、マーケティング部長、2018年ヤンマー建機専務、翌年同社社長といった要職を歴任。2022年ヤンマーホールディングス取締役CDOに就任した。東京大学理学修士、コロンビア大学MBA。
講演で奥山取締役は、「ヤンマーのデジタル戦略の方向性は、お客様への新たな価値の創出、業務品質・効率の改善のためにデジタルを最大限活用することを目指しデータに基づいた経営のために必要なプロセス文化の変革であるとし、重点取組み事項として①インフラ整備とセキュリティの強化②データ基盤の再構築・基幹システムの刷新③草の根DX施策・グループ展開(Quick win)⑤AI・データ活用・分析の5項目を挙げ、説明した。更に完全な私見としながら、AI・デジタルの進化を踏まえた将来の方向性を語った。聞く機会の少ない最先端のAIの話に、皆、真剣に聞き入った。
休憩を挟み、営業表彰(国内)。昨年は米価上昇により、収益の改善が図られた一方で、農業の現場では農業生産性の向上が引き続き大きな課題であり、農業機械の進化とスマート農機を中心に効率の高い農作業の重要性が高まった1年でもあった。そのような大きく変化する環境の中、攻めの営業、サービスに取組み優秀な実績を上げた特販店33店に50の表彰を行った。所司ヤンマーアグリ社長、小野寺ヤンマーアグリジャパン社長が一人ひとりに表彰楯と目録を手渡し感謝の意を伝えた。優秀経営賞には岩手県の阿部農機、茨城県の鹿行シバウラ、滋賀県の伊関商会、京都府の増田機械、兵庫県の伊藤農機、沖縄県の砂川鉄工ヤンマーが輝いた(表彰店別掲)。
続いてExcellentAward。海外9カ国から19社を招き表彰。所司ケマル社長と上田啓介副社長から表彰楯と副賞を一人一人に手渡し、それぞれの国の言語で感謝を伝えた。
閉会にあたり、西坂農機の西坂社長が特販店代表として挨拶。棹尾を飾った(別掲)。
ヤンマーHD・山本代表取締役挨拶 HANASAKAの価値観

昨年は物価高、円安の加速、また、農業においては、気候変動、人口増加による食糧需要の増大など、依然として市場環境は厳しく、多くの課題に直面した一年でした。このような不安定な状況にも関わらず、お客様の抱えている課題に寄り添い、解決に向けご尽力を頂いておりますことに改めて御礼申し上げます。
さて、私たちヤンマーグループは「A SUSTINABLE FUTURE」の理念のもと〝人間〟と〝自然〟の豊かさを両立した〝新しい豊かさ〟を創り出すために食料生産とエネルギー変換の分野で挑戦を続けて参りました。
昨年の本大会では、2050年までに環境負荷フリー、GHGフリーを実現するための宣言、〝Yanmar Green Challenge 2050〟の取組みを紹介しました。その後も環境へのソリューションは多様化し、私たちが解決しなければならない領域はますます広がっています。これまでのやり方に捉われない新しい技術・知見・発想を掛け合わせ、お客様も、私たち自身も心躍るようなソリューションを生みだせるよう挑戦を続けて参ります。これらの挑戦を支えるのは、創業以来変わらぬDNAであり、先ほどのミュージックビデオにも象徴される「HANASAKA」の価値観です。パートナーである皆さまにおかれましては、今後ともお力添えを賜り、農業の未来をワクワクできるものに変えていくため、共にチャレンジして参りましょう。
YAJ・所司社長挨拶 新たな取組みを創出 不確実な時代を勝ち抜く

昨年はロシアによるウクライナ侵攻やパレスチナ紛争の長期化、世界各国のリーダー交代など、世界情勢には多くの変化がありました。また日本では地球温暖化を思わせる猛暑、令和の米騒動と呼ばれた米不足と米価上昇、生産資材の高止まりや人手不足の深刻化に加え、改正食料・農業・農村基本法の施行など、農業の持続可能性の大切さが改めて認識された年でもありました。
最初に、我々をとりまく事業環境についてお話をしたいと思います。
世界の農業を取り巻く環境については、昨年のグローバル大会にてお伝えした通りです。2050年には人口は20%増加して約100億人になり、耕作地面積は3%増加にとどまり、そして農業人口は13%減少すると言われております。環境負荷を低減しながら食糧を増産する。その困難な課題に取り組まなければ持続可能な未来を実現できません。一方足元では、米国新政権誕生やグローバルサウスの台頭により、政治・経済面を中心に世界情勢の更なる変化が想定されます。
また、デジタル技術・脱炭素技術の発展や、食料安全保障の対策強化、世界的な物価上昇などのトレンドは、継続するものと思われます。つまり、政治・経済・環境・テクノロジーのどれもが急速に変化しているということです。
加速度的な変化が複雑に絡み合い、世界の不確実性は年々高まっています。このような不確実な世界は、私たちにとって体験したことのない、未知のものです。
未知は不安なものである一方で、可能性でもあります。そして、その未知の可能性を応援し、みんなで未来をワクワクできるものに変えていく。創業当時から受け継がれるヤンマーの文化を私どもは「HANASAKA」と呼んでいます。山本代表や長屋CBOのお話にもありました通り、私たちはお客様にワクワクして頂けるような新しい価値やソリューションを提供して参ります。ここで既に動き出している新たな取り組みをいくつかご紹介します。
ヤンマーでは2050年までに環境負荷フリー、GHGフリーを実現するための宣言、〝Yanmar Green Challenge 2050〟に取り組んでいます。
日本では、お客様の環境負荷低減と収益拡大に貢献するカーボンクレジットの創出に取り組み始めました。この取組みについては、フィリピンでも実証実験を行っています。
また、2023年度より水田における水管理の負担を軽減する機器を発売し、2024年度も多くのお客様にお届けしています。ヤンマーグリーンシステムでは大規模農業ハウスでの先進的栽培技術の実証実験に向け、提携を発表しました。これらの取組みは、現時点では私たちやお客様に大きな影響を及ぼさないように感じるかもしれません。しかしながら、10年後、20年後、30年後に振り返った際に、持続可能な農業の実現におけるターニングポイントとして認識される、非常に意味のあるものだと考えています。
次に、世界最大の人口を抱えるインドでの取組みです。インドでは既にITL社との緊密な戦略的パートナーシップで事業拡大に寄与しておりますが、それに加え、昨年9月に世界的な農機メーカーであるドイツCLAAS社のインド法人の全株式を取得し、新会社名をYAMINとしました。
現在、新しくヤンマーの仲間となった215名の皆さんとともに、ヤンマーブランドのコンバインやフォーレージハーベスターの生産準備を進めています。YAMINには、これまでCLAASブランド商品の生産で培った優れたノウハウと経験があり、ヤンマーアグリ事業拡大において、大きな力になってくれると確信しています。
我々には国内外に数多くの協業パートナーの皆様がおり、まだまだ大きなポテンシャルを秘めていると考えています。よって、これらのパートナーの皆様との連携をこれまで以上に強化し、新たな地域・新たなお客様への事業展開を共に開拓して参ります。
この一環として、昨年10月にはヤンマータイの設立45周年イベントでは、トンボ会各社様のご協力をいただき、3000名の来場者に対して数多くの新たな商材提案をいたしました。トルコで11月に開催したディストリビューター大会では、世界12カ国の皆様に、日本・韓国・タイ・トルコのパートナー様の商品を含めて紹介し、ビジネスマッチングを実施致しました。今後も、このような市場・お客様とパートナーの皆様をリンクしていく取り組みを継続していきます。
不確実な時代を勝ち抜くために、2025年も引き続き新たな取り組みを創生して参ります。私たちには可能性がある、未来がある。そう信じることがHANASAKAの第一歩だと考えています。
最後に、今日ここにお越しいただいている皆様は、私たちの掛け替えのない、不可欠なパートナーである、ということを改めてお伝えいたします。私たちと共に商品を開発・供給してくださる方々、その価値を日本や世界中のお客様に伝えていただく方々、そしてそのお客様を卓越したアフターサービスで守っていただいている方々、皆さま方ひとりひとりと共に、私たちヤンマーアグリはこの不確実な時代を勝ち抜き、成長して参ります。
迫農機商会 迫祐次氏、迫洋志氏 積極的に顧客開拓 地域の〝困りごと〟に全力

広島県東広島市の㈲迫農機商会は1986年に創業。地域の困りごとを商売の起点とし、確かな技術力と提案力で地域の農業に貢献してきた。メインの営業エリアは東広島市の豊栄町。水稲のほか転作による長ネギやキャベツ、タマネギなどの野菜、果樹など幅広い作物が生産されている。
同社代表は迫真治社長。30年以上もその務めを果たし、地域からの信頼も厚い。現在は息子の祐次氏、洋志氏が経営の主体となっており、今回の発表では兄弟二人で登壇し、中山間地域における取り組みや、今後の挑戦について語った。
「豊栄町は人口2800人で、2015年に557軒あった農家戸数は2020年には244軒にまで減少した。小規模農家が多数だが、農業法人が9社ほどある。最近では近隣の三次市、世羅町、三原市、呉市、広島市などの若手農家の方々ともお付き合いする機会が増えており営業エリアが拡大している。今では500軒以上のお客様と取引がある。その中で大切にしていることは、『地域社会に貢献するために存在する』と『情熱とロマンを持って行動する』で、これらを普段から実践している。農機具店の基本となる農機の修理については、高いサービス力を提供するために従業員全員が農業機械整備士2級以上を取得している。それに加えコミュニケーションを密にして地域の困りごとには全力で応えている。このような積み重ねで、既存のお客様から新規のお客様を紹介していただき、最小限の営業活動から最大の利益を生み出す経営サイクルができあがった」。
その中で積極的に顧客を開拓する特徴的な取り組みが行われている。「一つはヘリ防除の受託による新規顧客の開拓。7月〜9月にかけて年間延べ500haほどヘリによる水田防除を受託している。これをきっかけに農機の引き合いや整備の依頼を受け、ヤンマー製品のユーザーになっていただいている。2つ目は農作業マッチング。高齢農家から農作業の一部を依託したいという声が増えており、委託先が見つからない場合、弊社顧客となる法人経営の大規模農家を紹介している。農機の稼働時間が増え、点検整備や法人需要に繋がっている。3つ目は新規就農者へのサポート。資金力がなくても農作業が行えるように農機のレンタルサービスを行っている。これにより若手の新規就農者との付き合いが増え、数年後は農機購入に繋がっている。4つ目は田植機やコンバインのお預かり。点検整備をご依頼いただいたお客様を対象に次のシーズンまで機体を預かっている。出庫時には指定の場所まで機体をお届けすることで、稼働直前の試運転となり、時期中のマシントラブルを極小化する」。
また農家戸数が減少する中で、未来に繋がる店作りを模索し、新たな取り組みも始めている。「一つは地域の困りごとを起点としたビジネスを作ること。ドローンでの作業が増える中、ドローンを購入していただいた方への作業委託を考えている。また草刈作業も仲介したいと考えている。2つ目は農機の大型化、高性能化に伴い求められるサービス力のさらなる向上。3つ目は他のエリアとの交流を活発化すること。SNSの運用に力を入れ、広い視点でノウハウを蓄積していきたい」と、今後も挑戦していく姿を力強く示した。
ヤンマーHD・長屋取締役挨拶 未来の〝ありたき姿〟 〝人〟が中心となるブランド

「ヤンマーブランドは〝INCLUSIVE BRANDING〟だと考えている。〝HANASAKA〟をベースに、社内のみならず、社外企業、一般生活者も含めて全てステークホルダーとして考え、それぞれを巻き込みながら、ブランドを作り、人々に共感・信頼してもらえる機械、サービス、デザインを目指していく。
デザインフィロソフィは『本質デザイン(Intrinsic Design)』。形や様式にとらわれず、物事の本質を追い求める。表現形態としてのディレクションは『柔和剛健(Gentleness and Toughness)』を掲げた。壊れにくく信頼性の高いプロダクトと人に優しいことがポイントになる。重労働から人々を解放したいという創業者の精神を受け継ぎ、柔らかく人々に寄り添いながら課題に力強く立ち向かっていくことを方向性としてあげている。
これらを未来のビジョンとして、ヤンマーの〝ありたき姿〟を視覚化したものが〝YANMAR PRODUCT VISION(YPV)〟だ。そこには効率化などに繋がる設計思想の要素をプラットフォーム化できないのかという想いも込められている。ヤンマーのメインステージであるLAND、CITY、SEAの領域で、各事業と連携し、取り組みを進めた。その時、重要になるのが〝ヒューマン〟だ。人を基軸として考える中で、機械とは、サービスとはどうあるべきかというビジョンを構築すると共に視覚化を試みた。これにより様々な要素が抽出でき、それを製品へとフィードバックするというサイクルがスムーズに回っていけば、デザインプラットフォームが構築できるのではないかと思う。そうなれば共通化、統一化が進み、無駄が削減でき、よりサステナブルな未来に繋がるのではないかと考えている」。
次ぎに先にあげた3つの領域でどのような提案が行われているのかを解説。まずはアグリに関わる部分としてLANDのカテゴリーを紹介した。「本日ロビーにコンセプトモデルを展示しているが、YT3相当の車格で、あらゆるパワートレーンに対応し、冷却系レイアウトを刷新、エンジンルームを圧縮して再構築した。それによりキャビンの位置を前方に移動させることが可能となり、リヤタイヤとキャビンの干渉が緩和され自由度の高いトレッドを確保することができた。狭いあぜ道にも対応できる。また無人化への対応を見据え、エアレスタイヤを採用。キャビンを取り除いた無人機へとコンバートできるプラットフォームとしても、全体的なシミュレーションを行った」。
ロビーに展示されたコンセプトモデルには、ハンドルがなく、大型の液晶モニターと座席の両側に2つの操作レーバーがあるだけのスッキリとしたデザイン。またエンジンルームが半透明でエアレスタイヤのフォルムが目を引き、未来の姿を印象づけた。
「CITYでの取り組みでは、トラクタのキャビンを建機にも応用できるのではないかということで、3.5tクラスにキャビンの流用を考えている。加えてマルチトラックの多輪駆動を組み入れて提案を行っている。違う領域の製品においてもプラットフォームを共有していくことによって、コストダウンを図っていくことができる。SEAの領域では、モノハルフォイリングの提案を行っている。セイルが自動制御され、電動モーターを補助電力にしている。ヤンマーとしてセイリングを応援しているが、自然と人間との共生、新しい豊かさが表現できないかという一つの象徴として考えている」。
ビジョンが先行すると夢物語と憂慮される場合もあるとし、その上でアップルコンピュータを例に取り「iPadなどはコンセプト動画の方が先にでき、エンジニアリングが後から追いかけて完成している。同様にビジョンを組み立ててそれを実現していくと言う形で未来を作っていくことができないのかという試みになる。今後もこれらを皆さんと一緒に育てていきたい」と熱く会場内に語りかけた。
また「これらを進める上で一番大事なものは〝人〟だ。〝人〟が中心になっているブランドだと認識しており、プロダクションビジョンの一番は〝ヒューマン〟であり、人と機械の関係についても提案させていただいた。ヒューマン・マシーン・インターフェースのチームと共に取り組み、トラクターでは周囲で稼働する無人機を、走る管制塔としてマルチビジョンで制御していくスタイルを提案した」。
さらに〝人〟を中心にする上で『HANASAKAの精神』が重要になるとし、壇上にはそれを象徴するキャラクター『ヤン坊マー坊』が登場した。〝心を動かし、未来を動かす〟がコンセプトとして、新しく生まれ変わったヤンマーグループの企業マスコットキャラクターで、未来の可能性に一緒にチャレンジすることで、次世代層の未来への不安や悩みを、やりたいことを見つけ実現する力に変える存在を目指している。最後に「ヤンマーのフィロソフィを伝えていく存在として、共に頑張っていきたい」と力強く語った。
YTM・アリ オズポラット氏 目標は売上高倍増 グローバル展開を力にして
アグリ事業を柱として産業用エンジン事業、エネルギーシステム事業などを展開しているのがヤンマートルコマシナリー(YTM)。その中で特にアグリ事業は急激に成長し、2021年にはトラクターの組み立てを開始、2023年には工場を拡張した。積極的な展開のもと、トルコ国内シェアを急激に伸ばし、過去5年で売上高が約10倍へと伸張。またその活動地域は国外にも伸び、東欧や中東、北アフリカにまでエリアを拡大している。
壇上にはアグリビジネスの新規事業開拓や輸出拡大に携わっているアリ・オズポラット氏が立ち、その取り組みについて語った。「弊社は2017年に設立され、2019年にはインドベースのソリスブランドをトルコのマーケットに投入した。2021年にはYT AGRIブランドを設立し、農業関連の機器を世界的に展開することが可能となった。トルコ国内のマーケットシェアは今年度3.8%に達する見込み。2030年までに10%まで伸ばしたい。5年前、トルコに代理店は一つも存在していなかったが、2024年には71ディーラーまで達した。それに加えて195のサービスショップがあり、アフターサービスをカバーしている。
2030年までに事業量を2倍にする予定で、それを達成するためにはサプライヤーベースを拡張し、新しいパートナーシップを作ってネットワークを多様化することが必要。また高い品質の製品をつくり、プロダクトを増やさなければならない。イノベイティブで信頼性のあるソリューションを展開し、カスタマーネットワークを成長させ、信頼性を強固にして新しいマーケットに投入する」。
トルコ国内での積極的な展開に加えて、国外への取り組みが大きな特長。「グローバルな展開では14の国のディストリビュータの方々と関係を築いている。またYTMはグローバル販売代理店会議を2024年の11月にイスタンブールとイズミルで開催した。このイベントにはYAGおよび、複数の大陸にまたがる14カ国の販売代理店の代表者が集まった。パートナーシップを深め、ビジョンを共有し、グローバル市場でのポジション強化を図った。さらに弊社機械の革新的な設計と信頼性を紹介することができた。本会議は我々が成長と革新に向けて、共に歩んでいく上で、重要なマイルストーンとなった」。
このグローバルな成長をサポートするために、ソーシャルメディア広告、SEO対策などのデジタルマーケティングや多言語によるカスタマーサービスを実施。また「商品ラインナップの充実としては新しい顧客ニーズに対応するため市場調査の実施や、サプライヤーと協力して革新的な製品を共同開発している」。
昨年の代理店会議後、販売網の広がりがあり、セルビア、ウクライナ、ジョージア、アゼルバイジャンなどへの事業拡大に加え、ペルーの市場に参入したことを大きな成果としている。「研究開発、物流、品質管理、アフターサービスの中心でYTMがハブとしての役割を担い、ステークホルダーの求めに効果的に応えようとしている。このような取り組みの結果、YTMは現在30カ国で7000を超えるお客様にサービスを提供している。またパワード・バイ・ヤンマーという戦略のもと、トルコ国内には、ヤンマーのエンジン・補助装置を搭載した発電機、投光器、建設機械、道路工事用の機械を、トルコ国外にはYAGの販売店代理店にドローン・発電機の販売を開始した」。YTMが2030年までに売上高を倍増させるためには、「サプライヤーベースの拡大、取扱商品の拡充、顧客ネットワークを広げることが必要。このような取り組みで着実に成長を続け、目標を達成したい。より明るく持続可能な未来を一緒に切り開いていこう」。強い意欲で、積極的な取り組みが進められる。
特販店代表挨拶(西坂農機)

昨年、地域計画の策定が始まりました。各市町村では、どのように農地を守り発展させていくかの検討を重ねていきます。地域計画は私達にとって将来のお客様を明確にする重要な政策です。今後、私達はお客様とどのようなお付き合いをさせて頂くべきか、そのヒントが本日の発表の中にあると感じました。
先ほどの迫農機様の事例発表では、たとえ直接儲けにならなくとも、地域社会の一員として、人と人とのつながりを大切にし信頼を積み上げていけば必要とされる存在であり続けられるということを改めて学ばせていただきました。従来の農機販売に止まらない新しい商売の可能性を示していただきました。
今後目まぐるしい変化が予想される市場環境において、変わってはいけない本質を守りつつ、時代の流れに柔軟に対応する不易流行を実践していきたいと思っています。
私にとって今の仕事は生きがいそのものです。皆さんもヤンマーさんと共に充実感を感じられる仕事を続けていきましょう。







