ISO規格に掲載 ロボ・自動化検査の方法・基準

農研機構は、このほど農業機械研究部門が実施しているロボット・自動化農機検査の方法・基準が国際基準に掲載されたことを明らかにした。
ロボット農機については、世界的には2018年、ISO(国際標準化機構)で、安全性に関する国際規格「ISO18497:2018(農業機械類及びトラクター高度に自動化された農業機械の安全―設計原則)」が策定・発行された。同規格はロボット農機全般を対象とした安全または安全装置の要件を記載した規格だったが、具体的な性能や安全性の評価方法等を示したものではなかった。
一方、わが国では、2017年に農水省が「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を策定、2018年には、ほ場での有人監視下で運用されるロボットトラクタの本格的な市販化がスタート。これを受け、農研機構では、安全性検査の一つとして、ロボット・自動化農機検査において、運転状態を表す表示器や遠隔操作装置の機能、人や障害物を検出したときの安全機能などの検査を実施している。これまでロボット農機は3機種11型式、自動化農機は4機種91型式が認証されている。
こうしたなか、ISO18497:2018の発行当初に比べAIやGNSS、人・障害物検出センサなどの技術が進展。これらの技術を使ったロボット農機に対応した、より詳細な安全要件や性能、安全性の評価を定めることが求められるようになってきた。このため、2021年からISO TC23(農林業用トラクター及び機械を扱う専門委員会)/SC19(農業用電子設備を扱う分科委員会)/WG8(安全と保安を扱う作業グループ)で同ISOの改定作業がスタート。
農研機構では、同作業グループに担当者をエキスパートとして派遣。日本農業機械工業会ロボット農機分科会の協力を得て、安全性の検査方法・基準の国際規格として、すでに検査実績がある農研機構の「ロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び基準」を同ISOの改訂版に掲載することを提案。
作業グループでの協議で、農研機構が世界に先駆けてロボット農機の安全性確認に主眼をおいた検査を実施し、すでに数多くの認証を行っているという実績が高く評価され、ロボット農機の検査方法・基準がISO規格に掲載されることとなった。
国際規格に掲載されることで今後、海外の農機メーカーが日本向けのロボット農機の製造・販売を検討する際に農研機構の検査基準が考慮されることや、日本の農機メーカーによるロボット農機輸出への貢献が期待される。
ロボット農機については、世界的には2018年、ISO(国際標準化機構)で、安全性に関する国際規格「ISO18497:2018(農業機械類及びトラクター高度に自動化された農業機械の安全―設計原則)」が策定・発行された。同規格はロボット農機全般を対象とした安全または安全装置の要件を記載した規格だったが、具体的な性能や安全性の評価方法等を示したものではなかった。
一方、わが国では、2017年に農水省が「農業機械の自動走行に関する安全性確保ガイドライン」を策定、2018年には、ほ場での有人監視下で運用されるロボットトラクタの本格的な市販化がスタート。これを受け、農研機構では、安全性検査の一つとして、ロボット・自動化農機検査において、運転状態を表す表示器や遠隔操作装置の機能、人や障害物を検出したときの安全機能などの検査を実施している。これまでロボット農機は3機種11型式、自動化農機は4機種91型式が認証されている。
こうしたなか、ISO18497:2018の発行当初に比べAIやGNSS、人・障害物検出センサなどの技術が進展。これらの技術を使ったロボット農機に対応した、より詳細な安全要件や性能、安全性の評価を定めることが求められるようになってきた。このため、2021年からISO TC23(農林業用トラクター及び機械を扱う専門委員会)/SC19(農業用電子設備を扱う分科委員会)/WG8(安全と保安を扱う作業グループ)で同ISOの改定作業がスタート。
農研機構では、同作業グループに担当者をエキスパートとして派遣。日本農業機械工業会ロボット農機分科会の協力を得て、安全性の検査方法・基準の国際規格として、すでに検査実績がある農研機構の「ロボット・自動化農機検査の主要な実施方法及び基準」を同ISOの改訂版に掲載することを提案。
作業グループでの協議で、農研機構が世界に先駆けてロボット農機の安全性確認に主眼をおいた検査を実施し、すでに数多くの認証を行っているという実績が高く評価され、ロボット農機の検査方法・基準がISO規格に掲載されることとなった。
国際規格に掲載されることで今後、海外の農機メーカーが日本向けのロボット農機の製造・販売を検討する際に農研機構の検査基準が考慮されることや、日本の農機メーカーによるロボット農機輸出への貢献が期待される。

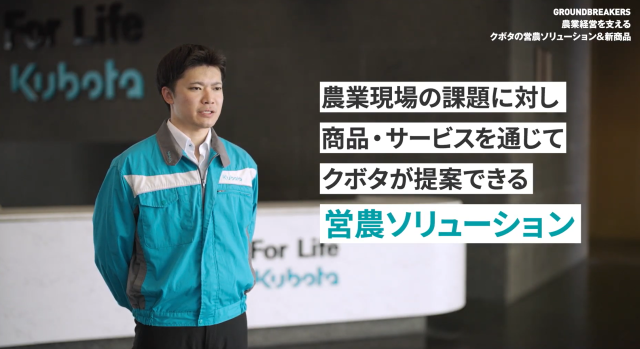
.JPG)

.jpg)




