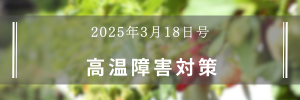農水省、不測時の食料安全保障へ 来通常国会で法制化 検討会が取りまとめ

生産者の自主性を重んじつつ生産転換の要請など
ロシアによるウクライナ侵略や中東紛争、中国による水産物の輸入規制など世界的に情勢が変化、また気候変動も激化を続けているなか、いかに食料安全保障を確保していくか。農水省では検討会を立ち上げ、議論を進めてきた。このほど、検討会の取りまとめが行われ、方向性が示された。事態を4つの段階に分けて、それぞれのタイミングで行う措置を示している。事態によっては、事業者の自主性を尊重しつつも、生産転換の要請を行う。今後来年の通常国会での法制化を目指す。
今年6月に決まった「食料・農業・農村政策の新たな展開方向」では、不測時の食料安全保障について、対応根拠となる法制度を検討する」とされており、これを踏まえて設置されたのが、「不測時における食料安全保障に関する検討会」。8月以降、これまで5回開かれており、12月6日の第6回で議論の結果を取りまとめた。
今回の取りまとめは、様々なリスクに対応可能なよう議論し、事業者の自主性を尊重したスキームをコンセプトとしていること。そして、兆候が起こった段階から素早く対応し、政府一体となって総合的に対応していくことがポイントとなっている。
事態の段階を、平時、食料供給の兆候、食料供給への大きな影響発生などに分類
具体的な対策の全体イメージは上図の通りだが、事態の段階を①平時②食料の供給減少の兆候③食料の供給減少による大きな影響の発生(目安:不測時の対策の対象品目・資材(米、小麦、大豆(食用・油糧用)、その他の植物油脂原料(なたね、パーム油)、畜産物(鶏卵、食肉、乳製品)、砂糖及び肥料、飼料、種子・種苗、農薬燃油などの資材)の供給量が平時に比べ2割以上減少または買占めや価格高騰など国民生活・国民経済への支障の発生)④国民が最低限必要な食料が不足するおそれ(目安:供給熱量が1人1日あたり1900キロカロリー)――の4つに分けそれぞれ政府の体制・対応や主な措置をまとめている。
例えば②の兆候段階及び③の大きな影響の発生段階においては、生産段階では、「生産の拡大」に向け、国が生産拡大すべき量等を示し、生産者の自主性を尊重しつつ生産の要請を行う。また要請のみで生産量を確保できない場合は生産の計画作成の指示等を行うこととしている。また、④の不測のおそれの段階では、「生産の転換」について、生産者への要請を基本としつつ、要請では必要量が確保できない場合に限り、計画作成等の指示を行うこととしている。
これら生産に対する要請等を行う場合には、インセンティブ措置を設けることが示されている。
農水省では、これらの取りまとめをもとに、詳細について詰めの作業を進めつつ、次期通常国会での法案提出を目指すとともに、関係者への説明を行っていくこととしている。