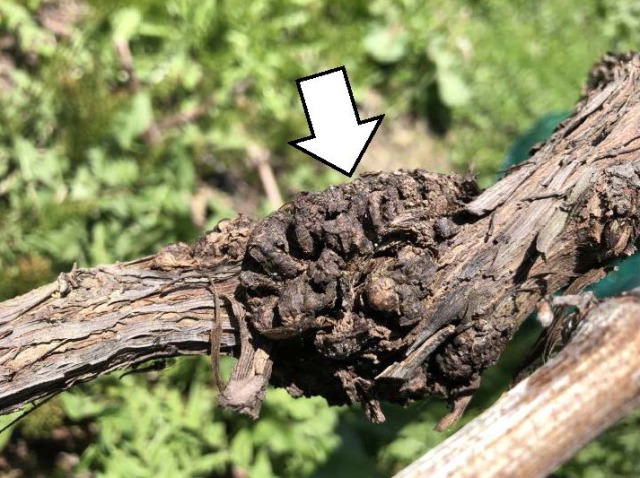下水汚泥の肥料利用 安全・品質確保し拡大へ

農水省及び国交省が連携して開催していた「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」において、これまでの議論の成果として、課題と取組の方向性を取りまとめた論点整理が公表された。論点整理では、目標を2030年までに堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増し、肥料の使用量(リンベース)に占める国内資源の割合40%に設定。各分野が連携しつつ安全性・品質を確保しながら利用拡大にむけて総力をあげて取組むこととした。
農業生産にとって欠かせない化学肥料ではあるが、その原料については、大半を輸入に依存している。しかし、近年の中国の輸出規制やロシアによるウクライナ侵攻などにより、肥料原料価格が高騰、農業生産が厳しい状況にさらされている。
このため、国内未利用資源の活用に向けてスタートしたのが、「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」だ。昨年10月にスタートした同検討会は、計3回開催されている。今回公表されたのは、これらのなかでの議論を論点整理としてまとめたもの。
取組の方向性としては、「肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、農水省、国交省、農業分野、下水道分野が連携し、安全性・品質を確保しつつ、消費者も含めた理解促進を図りながら、各関係者が主体的に下水汚泥資源の大幅な拡大に向けて総力をあげて取組む」と設定。目標は、昨年12月27日に決まった食料安全保障強化政策大綱に盛り込まれた「2030年までに堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増し、肥料の使用量(リンベース)に占める国内資源の利用割合を40%に」と設定した。
その実現に向けた関係者の役割については、国は肥料成分を保証可能な新たな公定規格の設定やリン回収の採算性向上・生産量確保に向けた技術開発、下水道事業者・肥料製造業者・農業者のマッチングによる流通経路の確保などに取組む。肥料製造業者の役割としては安全性・品質が確保された下水汚泥資源を原料として農業者のニーズに応じた肥料実用化やその製造設備の整備などに取組む―などとしている。
一方論点整理についてみてみると、「『汚泥肥料』に対する農業者や消費者のイメージの改善(ネーミングも含む)、未利用資源の地域循環としての意義のPRなど農業者や地域の理解醸成」については、国内肥料資源利用拡大対策等の事業で下水汚泥資源由来肥料を利用した圃場での効果検証の取組を支援する他、現場の取り組み事例発表や広報活動、シンポジウムの開催などについても取組むこととした。
また、「地域によって特別栽培米で汚泥肥料が使えないケースもあることへの対応」については、農水省のWEBサイトに掲載しているQ&Aに「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では汚泥肥料の使用を禁止していないことを追記するとともに、その旨を地方自治体に通知するとした。
「グローバルGAPの審査基準に『人糞尿を含む下水汚泥を使用しないようにしているか』という項目への対応」については、安全性が確保された下水汚泥資源の肥料利用が認められるよう、グローバルGAP国内関係者に働きかけを行うとともに、世界食品安全イニシアチブ(GFSI)の承認を得た日本発のGAP認証であるASIAGAPの普及を推進することとしている。
農業生産にとって欠かせない化学肥料ではあるが、その原料については、大半を輸入に依存している。しかし、近年の中国の輸出規制やロシアによるウクライナ侵攻などにより、肥料原料価格が高騰、農業生産が厳しい状況にさらされている。
このため、国内未利用資源の活用に向けてスタートしたのが、「下水汚泥資源の肥料利用の拡大に向けた官民検討会」だ。昨年10月にスタートした同検討会は、計3回開催されている。今回公表されたのは、これらのなかでの議論を論点整理としてまとめたもの。
取組の方向性としては、「肥料の国産化と安定的な供給、資源循環型社会の構築を目指し、農水省、国交省、農業分野、下水道分野が連携し、安全性・品質を確保しつつ、消費者も含めた理解促進を図りながら、各関係者が主体的に下水汚泥資源の大幅な拡大に向けて総力をあげて取組む」と設定。目標は、昨年12月27日に決まった食料安全保障強化政策大綱に盛り込まれた「2030年までに堆肥・下水汚泥資源の使用量を倍増し、肥料の使用量(リンベース)に占める国内資源の利用割合を40%に」と設定した。
その実現に向けた関係者の役割については、国は肥料成分を保証可能な新たな公定規格の設定やリン回収の採算性向上・生産量確保に向けた技術開発、下水道事業者・肥料製造業者・農業者のマッチングによる流通経路の確保などに取組む。肥料製造業者の役割としては安全性・品質が確保された下水汚泥資源を原料として農業者のニーズに応じた肥料実用化やその製造設備の整備などに取組む―などとしている。
一方論点整理についてみてみると、「『汚泥肥料』に対する農業者や消費者のイメージの改善(ネーミングも含む)、未利用資源の地域循環としての意義のPRなど農業者や地域の理解醸成」については、国内肥料資源利用拡大対策等の事業で下水汚泥資源由来肥料を利用した圃場での効果検証の取組を支援する他、現場の取り組み事例発表や広報活動、シンポジウムの開催などについても取組むこととした。
また、「地域によって特別栽培米で汚泥肥料が使えないケースもあることへの対応」については、農水省のWEBサイトに掲載しているQ&Aに「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では汚泥肥料の使用を禁止していないことを追記するとともに、その旨を地方自治体に通知するとした。
「グローバルGAPの審査基準に『人糞尿を含む下水汚泥を使用しないようにしているか』という項目への対応」については、安全性が確保された下水汚泥資源の肥料利用が認められるよう、グローバルGAP国内関係者に働きかけを行うとともに、世界食品安全イニシアチブ(GFSI)の承認を得た日本発のGAP認証であるASIAGAPの普及を推進することとしている。


 (1).jpg)