【特別寄稿】食の安全を科学で検証する ‐2‐ =東京大学名誉教授、食の安全・安心財団理事長 唐木英明=

一部週刊誌が、いたずらに食への不安を煽る連載を続け、それが物議をかもしている。いまさらと思う向きもあるやもしれないが、本紙では改めて食の安全とは何か、食の安全をどう理解すべきかを、この分野の第一人者である東京大学名誉教授、公益財団法人「食の安全・安心財団」理事長の唐木英明氏に科学的に解説してもらうことにした。本紙では回を分けこれを紹介していく。
====================================================================
作物に農薬が残留したら危険か
すべての化学物質が多量なら危険、微量なら安全であること、そして一生食べ続けても何の悪影響もない一日摂取許容量(ADI)を守ることで食品の安全を守ることをお話ししました(本紙5月11日号)。これを農薬に当てはめると、どうなるのでしょうか。
農薬の原液は高濃度なので、間違って摂取すると健康被害の可能性があります。昔の農薬は毒性が強く、自殺や殺人に使われたことがあるのですが、最近は安全性が高くなっています。とはいえ原液の取り扱いは注意が必要で、農水省の調査ではこのところ毎年数人の死者が出ています。原因の大部分は「保管管理不良、泥酔等による誤飲誤食」と記載されています。
原液を希釈して散布するときには、殺虫や除草の効果が得られるだけの濃度が必要です。散布した農薬は空気や光や微生物により分解されて消えていきます。だから繰り返し散布する必要があるのです。
「分解されない農薬を作ったら、一回の散布で済むじゃないか」と考える方がいるかもしれませんが、それは危険です。分解されなければ農作物に残留して食品安全の問題が起こります。土壌中に蓄積すれば、環境汚染を起こします。だから農薬は分解されるようにできています。
農薬の安全性試験について、Aという農薬を例にして、説明しましょう。まず、ラット、マウス、ウサギなどの実験動物に農薬Aを投与します。高濃度では肝臓、腎臓など様々な臓器に毒性が出ますが、低濃度ではなんの毒性も出ません。そのような試験を繰り返して、どの臓器にも毒性がない「無毒性量」を見つけます。
また、ラットを使って交配、妊娠、分娩、新生児の生育などの生殖機能の試験も行い、奇形などが起こらないことを確認します。
大事なことは、これらの試験で発がん性を疑う結果が出たら、Aを農薬として使う許可は得られないことです。だから、現在販売されている農薬のなかに発がん性のものは存在しません。
そのうえで、動物と人間の感受性の違いと、人間の個人差を考慮して、無毒性量の百分の一の量を一日摂取許容量(ADI)とします。
化学物質が体に作用するためには、細胞の受容体に結合することが必要ですが、ある程度以上の量がなければ結合できません。この量を「しきい値」と呼び、それがADIと考えられています。このADIが農薬Aの残留基準を決めるための基礎になります。ここまでの作業を内閣府食品安全委員会が行います。私も長年、ADIを決定するお手伝いしてきました。
次は農林水産省の出番です。農薬Aを使う作物をすべて実際に栽培し、どの時期に、どのくらいの量の農薬を散布したら、どのくらい作物に残留するのか調べます。
そして国民がこれらの農産物を食べる量の平均値を調べます。この二つから、農薬Aを使用した農作物をすべて食べたときに摂取する農薬Aの量を計算します。
その量がADIの八割を超えないように調整して、作物ごとの基準値が決まります。
他方、農薬Aを使わない作物は残留がゼロでなくてはいけないのですが、隣の畑から農薬Aが飛来することもあるので、確実に安全な量である0・01ppmという一律基準を設定します。
さらに詳しくは農水省のホームページを見てください。
====================================================================
====================================================================
作物に農薬が残留したら危険か
すべての化学物質が多量なら危険、微量なら安全であること、そして一生食べ続けても何の悪影響もない一日摂取許容量(ADI)を守ることで食品の安全を守ることをお話ししました(本紙5月11日号)。これを農薬に当てはめると、どうなるのでしょうか。
農薬の原液は高濃度なので、間違って摂取すると健康被害の可能性があります。昔の農薬は毒性が強く、自殺や殺人に使われたことがあるのですが、最近は安全性が高くなっています。とはいえ原液の取り扱いは注意が必要で、農水省の調査ではこのところ毎年数人の死者が出ています。原因の大部分は「保管管理不良、泥酔等による誤飲誤食」と記載されています。
原液を希釈して散布するときには、殺虫や除草の効果が得られるだけの濃度が必要です。散布した農薬は空気や光や微生物により分解されて消えていきます。だから繰り返し散布する必要があるのです。
「分解されない農薬を作ったら、一回の散布で済むじゃないか」と考える方がいるかもしれませんが、それは危険です。分解されなければ農作物に残留して食品安全の問題が起こります。土壌中に蓄積すれば、環境汚染を起こします。だから農薬は分解されるようにできています。
農薬の安全性試験について、Aという農薬を例にして、説明しましょう。まず、ラット、マウス、ウサギなどの実験動物に農薬Aを投与します。高濃度では肝臓、腎臓など様々な臓器に毒性が出ますが、低濃度ではなんの毒性も出ません。そのような試験を繰り返して、どの臓器にも毒性がない「無毒性量」を見つけます。
また、ラットを使って交配、妊娠、分娩、新生児の生育などの生殖機能の試験も行い、奇形などが起こらないことを確認します。
大事なことは、これらの試験で発がん性を疑う結果が出たら、Aを農薬として使う許可は得られないことです。だから、現在販売されている農薬のなかに発がん性のものは存在しません。
そのうえで、動物と人間の感受性の違いと、人間の個人差を考慮して、無毒性量の百分の一の量を一日摂取許容量(ADI)とします。
化学物質が体に作用するためには、細胞の受容体に結合することが必要ですが、ある程度以上の量がなければ結合できません。この量を「しきい値」と呼び、それがADIと考えられています。このADIが農薬Aの残留基準を決めるための基礎になります。ここまでの作業を内閣府食品安全委員会が行います。私も長年、ADIを決定するお手伝いしてきました。
次は農林水産省の出番です。農薬Aを使う作物をすべて実際に栽培し、どの時期に、どのくらいの量の農薬を散布したら、どのくらい作物に残留するのか調べます。
そして国民がこれらの農産物を食べる量の平均値を調べます。この二つから、農薬Aを使用した農作物をすべて食べたときに摂取する農薬Aの量を計算します。
その量がADIの八割を超えないように調整して、作物ごとの基準値が決まります。
他方、農薬Aを使わない作物は残留がゼロでなくてはいけないのですが、隣の畑から農薬Aが飛来することもあるので、確実に安全な量である0・01ppmという一律基準を設定します。
さらに詳しくは農水省のホームページを見てください。
====================================================================
【唐木英明(からき・ひであき)氏】
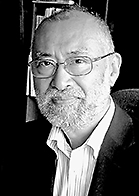
農学博士、獣医師。1964年東京大学農学部獣医学科卒業。87年東京大学教授、同大学アイソトープ総合センター長を併任、2003年名誉教授。現職は公益財団法人食の安全・安心財団理事長、公益財団法人食の新潟国際賞財団選考委員長、内閣府食品安全委員会専門参考人など。
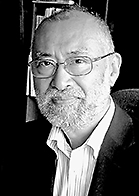
農学博士、獣医師。1964年東京大学農学部獣医学科卒業。87年東京大学教授、同大学アイソトープ総合センター長を併任、2003年名誉教授。現職は公益財団法人食の安全・安心財団理事長、公益財団法人食の新潟国際賞財団選考委員長、内閣府食品安全委員会専門参考人など。
専門は薬理学、毒性学(化学物質の人体への作用)、食品安全、リスクマネージメント。1997年日本農学賞、読売農学賞を受賞。2011年、ISI World's Most Cited Authorsに選出。2012年御所において両陛下にご進講。この間、倉敷芸術科学大学学長、日本学術会議副会長、日本比較薬理学・毒性学会会長、日本トキシコロジー学会理事長、日本農学アカデミー副会長、原子力安全システム研究所研究企画会議委員などを歴任。








