基本法等説明会 生産性向上に向け スマート技術の導入促進

先ごろ閉会した今年度の通常国会で成立した食料・農業・農村基本法。わが国の食料供給をどのようにしていくかという非常に重要な方向性を示すものであり、単に関係者だけでなく、広く国民の理解が必要なものだ。
このため、農水省では全国各ブロックで説明会を実施する予定であり、7月10日にはその皮切りに、東京都千代田区の本省講堂で「食料・農業・農村基本法改正法等に関する説明会」が開催された。
説明会では、始めに舞立昇治政務官が挨拶に立ち、「基本法は、世界とわが国の食を巡る情勢が大きく変化していくことを踏まえ、時代に相応しいものとなるよう改正を行わせていただいた。食料の持続的な供給を行っていくためには、幅広い関係者の皆様のご理解とご協力、ご支持のもとで、一体となって取組んでいくことが重要と考えている」と述べた。
その後、農水省が基本法及び関連3法案について説明。基本法の具体的施策としては、農業生産基盤等の確保のため、第22条に「農産物の輸出の促進」を新設し、輸出産地の育成、品目団体の取組の促進などを図っていく。また、「環境と調和のとれた食料システム」については、第32条に「環境への負荷の低減の促進」を新設。環境への負荷の低減に資する生産方式の導入などを進める。
更に、基本法では、農業生産の方向性として、「生産性の向上」「付加価値の向上」「環境負荷低減」を位置づけ、第30条に「先端的な技術等を活用した生産性の向上」を新設。スマート技術等を活用した生産・加工・流通方式の導入を促進する。
また、令和6年度中に策定する次期基本計画に関しては、食料自給率その他食料安全保障の確保に関する事項の目標の達成状況を少なくとも年一回調査・公表し、PDCAを回す新たな仕組みを導入する、とした。
一方、スマート農業技術活用促進法については、農業者等向けの生産方式革新実施計画、開発供給事業者向けの開発供給実施計画の認定制度を創設。日本政策金融公庫の長期低利融資、行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認)、農研機構の研究開発設備等の共用等(開発供給実施計画)などの支援措置を講じる。
同法は10月1日に施行、国の基本方針を公表。併せて施行令や申請書様式等も公表する、などと説明した。
このため、農水省では全国各ブロックで説明会を実施する予定であり、7月10日にはその皮切りに、東京都千代田区の本省講堂で「食料・農業・農村基本法改正法等に関する説明会」が開催された。
説明会では、始めに舞立昇治政務官が挨拶に立ち、「基本法は、世界とわが国の食を巡る情勢が大きく変化していくことを踏まえ、時代に相応しいものとなるよう改正を行わせていただいた。食料の持続的な供給を行っていくためには、幅広い関係者の皆様のご理解とご協力、ご支持のもとで、一体となって取組んでいくことが重要と考えている」と述べた。
その後、農水省が基本法及び関連3法案について説明。基本法の具体的施策としては、農業生産基盤等の確保のため、第22条に「農産物の輸出の促進」を新設し、輸出産地の育成、品目団体の取組の促進などを図っていく。また、「環境と調和のとれた食料システム」については、第32条に「環境への負荷の低減の促進」を新設。環境への負荷の低減に資する生産方式の導入などを進める。
更に、基本法では、農業生産の方向性として、「生産性の向上」「付加価値の向上」「環境負荷低減」を位置づけ、第30条に「先端的な技術等を活用した生産性の向上」を新設。スマート技術等を活用した生産・加工・流通方式の導入を促進する。
また、令和6年度中に策定する次期基本計画に関しては、食料自給率その他食料安全保障の確保に関する事項の目標の達成状況を少なくとも年一回調査・公表し、PDCAを回す新たな仕組みを導入する、とした。
一方、スマート農業技術活用促進法については、農業者等向けの生産方式革新実施計画、開発供給事業者向けの開発供給実施計画の認定制度を創設。日本政策金融公庫の長期低利融資、行政手続の簡素化(ドローン等の飛行許可・承認)、農研機構の研究開発設備等の共用等(開発供給実施計画)などの支援措置を講じる。
同法は10月1日に施行、国の基本方針を公表。併せて施行令や申請書様式等も公表する、などと説明した。

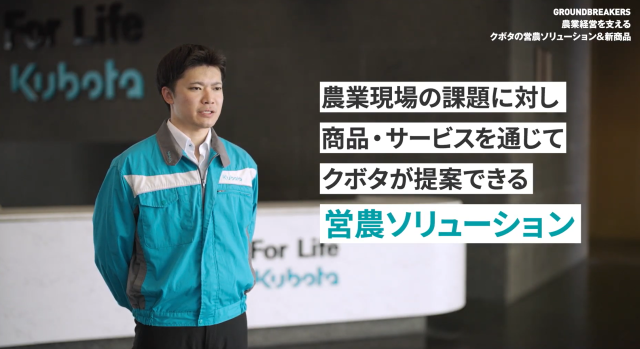
.JPG)

.jpg)




