陸内協技術フォーラム カーボンニュートラルへの技術紹介 軽油へのOME混合等
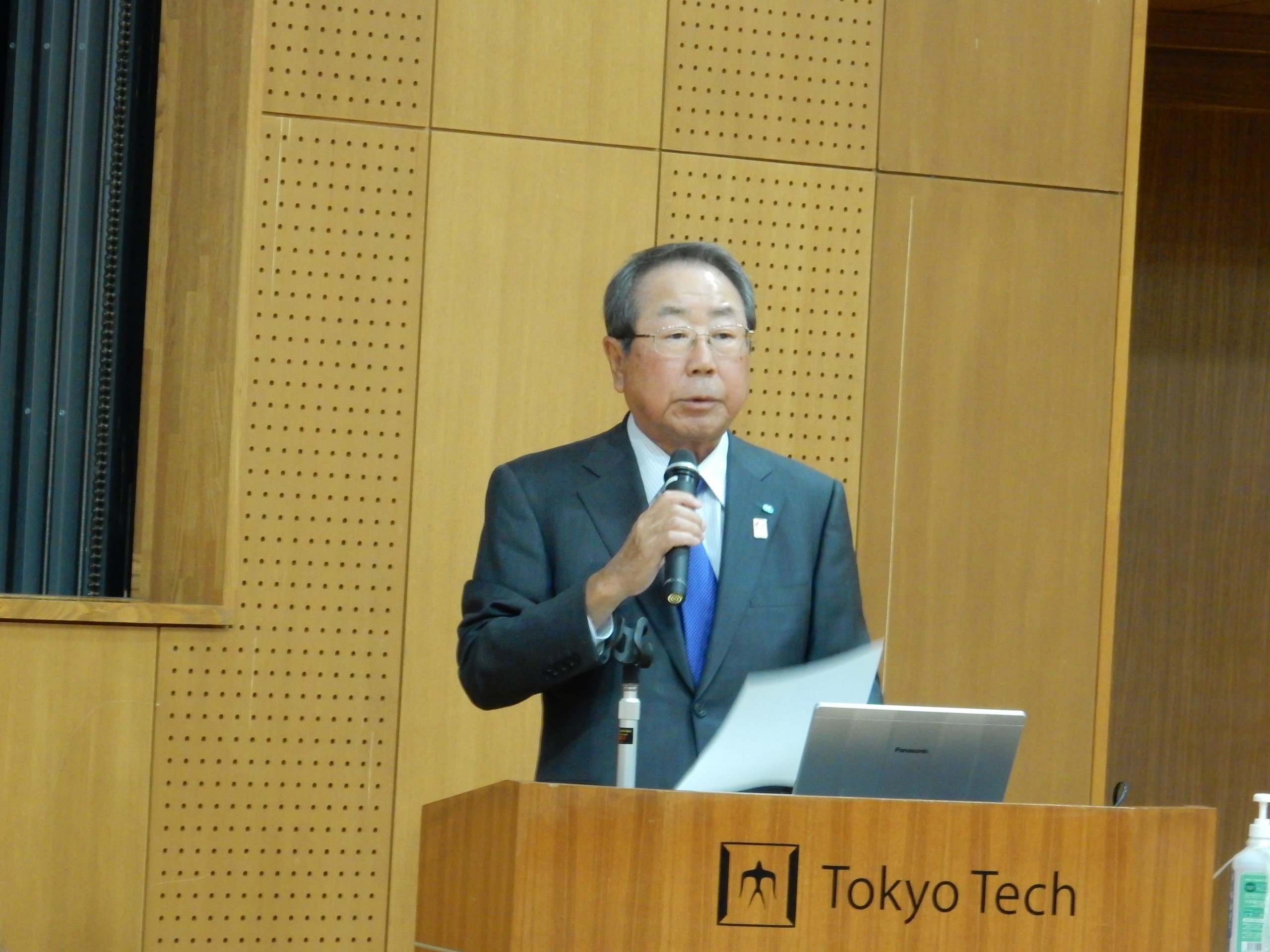
エンジン性能の向上やカーボンニュートラルに向けての有力な技術紹介
日本陸用内燃機関協会(木股昌俊会長)は10月25日、東京都目黒区の東京工業大学ディジタル多目的ホール及びオンラインの併用で「第23回技術フォーラム2023」を開催した。当日は会員だけでなく、会員外からの参加もあり、オンライン・会場参加をあわせて150人超が参加した。
はじめに木股会長が挨拶。「2020年10月の菅前首相の2050年カーボンニュートラル宣言により国内では脱炭素に向けた議論が急速に高まってきた。自動車の世界は電動化が強く推進される一方、当協会が担当する産業用機械に搭載される内燃機関は手で持てるほど軽い用途や長時間ノンストップで動かす必要のある機械などが多くある。また、電気の通っていない場所で使われることも多く、充電所まで自分で移動できない機械もある。このような用途には、未来においても内燃機関が役立つと確信しており、今後も積極的な研究開発が必要だと考えている。こうした背景から今回の講演では3名から講演いただく。いずれもエンジン性能の向上やカーボンニュートラルに向けての有力な技術紹介となる」と述べた。
その後、講演。カワサキモータース汎用エンジンディビジョンの小林靖卓氏は「芝刈機用空冷VツインエンジンFX820Vの開発」。従来機種に対する信頼性を維持しながら、高出力・低燃費化と排ガス値の抑制をバランスさせることを目指したプロ向け乗用芝刈機用汎用エンジンについて、コンセプトや仕様、排ガス・燃料消費率、信頼性・耐久性などを紹介した。
いすゞ中央研究所の森田真一氏は「軽油へのOME混合が燃料性状とディーゼル機関性能に及ぼす影響」がテーマ。再生可能エネルギーの電気を用いて生成されたH2と工場などから排出されるCO2から生成されるカーボンニュートラル燃料には、FT(フィッシャー・トロプシュ)燃料、e―メタン、e―メタノール、DME(ジメチルエーテル)/OME(オキシメチレンエーテル)など種類がある。このうち、OMEは常温で液体のため、ハンドリングが良く、含酸素燃料のため軽油に対し排気特性に優れる可能性がある。一方、軽油に比べ発熱量が低い、ゴム製品の膨潤作用、燃料製造効率・コストなどの懸念事項から軽油への少量混合(ドロップイン)での活用が想定される。このため、OMEを混合した軽油を既存のディーゼルエンジンに使用した際の影響を調査、今回報告した。
このほか、石油エネルギー技術センター(JPEC)石油基盤技術研究所合成燃料研究室の岡本憲一氏が「液体合成燃料の一貫製造プロセスおよび燃料利用研究開発」をテーマに講演を行った。
講演後には、慶應義塾大学の飯田訓正名誉教授が司会となり、北海道大学の小川英之教授、東京工業大学の小酒英範教授、千葉大学の森吉泰生教授、東京都市大学の三原雄司教授に加え、講演者が参加しパネルディスカッションが行われ、盛況だった。

.jpg)
_photo260202-1-1.jpg)






