〝メイズ〟生産拡大 生産者協会を設立 機械への導入支援を期待
飼料価格の高騰から国産飼料、特に供給の少ない濃厚飼料については、国内生産への期待が高まっている。そうしたなか、子実用とうもろこしの普及に向け全国初となる生産者団体「日本メイズ生産者協会(JMFA)」が発足。8月25日には港区のベルサール虎ノ門ホールで設立記念シンポジウムが開かれた。
記念シンポには全国から関係者など170人が参加した。開催にあたり代表理事の柳原孝二氏が挨拶。祝辞は衆議院議員で前農林水産副大臣の中村裕之氏。
記念講演は藤木眞也・農林水産大臣政務官による「日本農業と子実用とうもろこしへの期待」。藤木政務官は自らが畜産農家だった経験も踏まえ「子実用とうもろこしはこれまで水田に反当たり3万5000円の助成金しかなかったが、今年からは水田リノベ事業などで5万円にまでなった。この事業により、宮城県や福岡県などでJA単位の取組がスタート。来年には佐賀県でも取り組みたいという意向を聞いている。国産の子実用とうもろこしは畜産業を持続可能なものにしていくためには必要不可欠であり、今はまだ全体の使用量の1%にも満たない状況かもしれないが、こうして少しずつ拡大していけば、伸びしろの大きい作物だと思う」などとした。
講演では、柳原代表理事は生産者の立場から現状について報告。作付面積は2022年(暫定値)で1839haと前年から約700haの増加となっている。その生産拡大の理由として効果ある茎葉処理除草剤が多く雑草防除が比較的容易、土壌環境改善に効果的、有機質還元による増収効果が期待されるなど挙げた。そのうえで、担い手が今後更に減少するなか労働生産性が高い、飼料用米の財政負担の軽減、食料自給率への寄与などの要因からさらなる生産拡大が必要だとした。一方、課題として①大区画ほ場整備による生産性向上②水田リノベーション事業や高収益作物の支援を受けても現状の収量では生産費をカバーできるギリギリの状況③機械についてコンバインとコーンヘッダー、高精度な播種機、簡易貯蔵タンクなどへの導入支援が必要④流通体制の整備⑤品質の確保―などをあげた。
子実用とうもろこしは飼料としてだけでなく、食品利用としても期待が高い。今後どのような支援策が行われるのか、そしてそれによってどれだけ作付けが増えるのか注目が集まる。
記念シンポには全国から関係者など170人が参加した。開催にあたり代表理事の柳原孝二氏が挨拶。祝辞は衆議院議員で前農林水産副大臣の中村裕之氏。
記念講演は藤木眞也・農林水産大臣政務官による「日本農業と子実用とうもろこしへの期待」。藤木政務官は自らが畜産農家だった経験も踏まえ「子実用とうもろこしはこれまで水田に反当たり3万5000円の助成金しかなかったが、今年からは水田リノベ事業などで5万円にまでなった。この事業により、宮城県や福岡県などでJA単位の取組がスタート。来年には佐賀県でも取り組みたいという意向を聞いている。国産の子実用とうもろこしは畜産業を持続可能なものにしていくためには必要不可欠であり、今はまだ全体の使用量の1%にも満たない状況かもしれないが、こうして少しずつ拡大していけば、伸びしろの大きい作物だと思う」などとした。
講演では、柳原代表理事は生産者の立場から現状について報告。作付面積は2022年(暫定値)で1839haと前年から約700haの増加となっている。その生産拡大の理由として効果ある茎葉処理除草剤が多く雑草防除が比較的容易、土壌環境改善に効果的、有機質還元による増収効果が期待されるなど挙げた。そのうえで、担い手が今後更に減少するなか労働生産性が高い、飼料用米の財政負担の軽減、食料自給率への寄与などの要因からさらなる生産拡大が必要だとした。一方、課題として①大区画ほ場整備による生産性向上②水田リノベーション事業や高収益作物の支援を受けても現状の収量では生産費をカバーできるギリギリの状況③機械についてコンバインとコーンヘッダー、高精度な播種機、簡易貯蔵タンクなどへの導入支援が必要④流通体制の整備⑤品質の確保―などをあげた。
子実用とうもろこしは飼料としてだけでなく、食品利用としても期待が高い。今後どのような支援策が行われるのか、そしてそれによってどれだけ作付けが増えるのか注目が集まる。

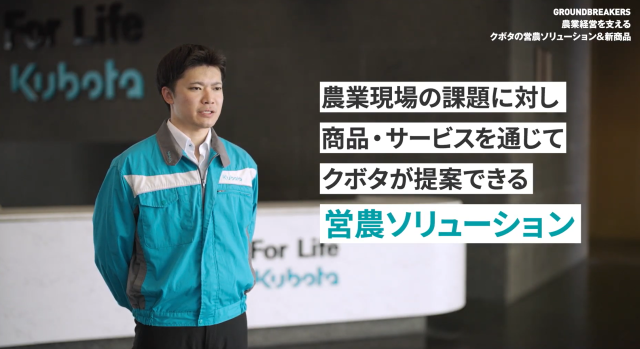
.JPG)

.jpg)




