気候変動で注目集めるバイオスティミュラント(BS)
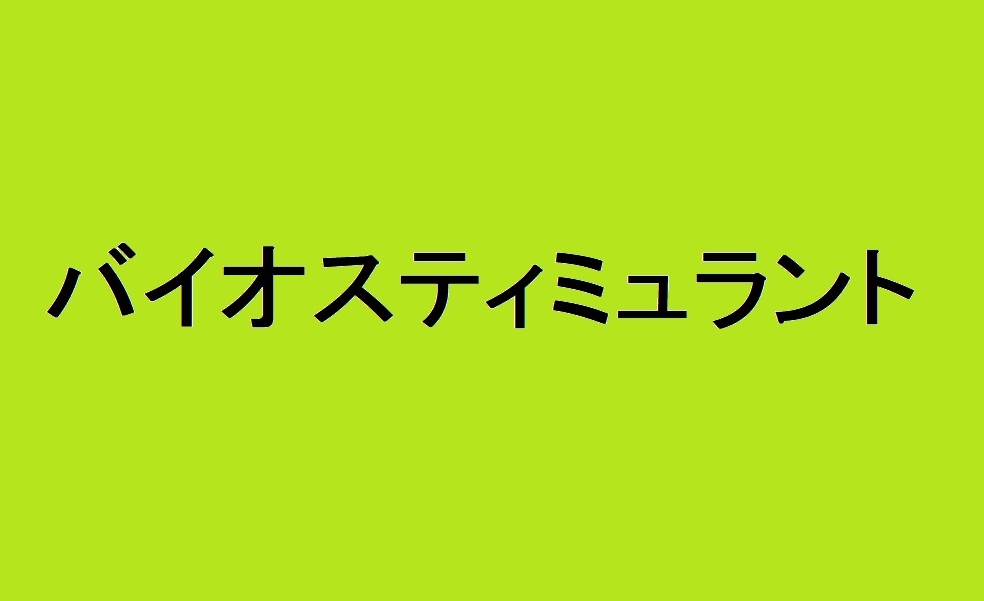
BSの位置づけと展望 業界あげ自主基準づくり
バイオスティミュラント(BS)と呼ばれる新しい資材カテゴリーは、近年、農業資材の展示会などで頻繁に取り上げられるようになってきた。
BSは肥料や農薬とは異なり、高温や干ばつなど、農作物が受けるストレスを緩和する役割を果たす。地球温暖化対策など気候変動に対応する資材・技術として注目が集まっている。特に近年、高温が農作物に与える影響は顕著である。これまで暑さ対策が不要であった新潟など北陸地方では、暑さに弱いコシヒカリで白未熟粒の発生が多くなり、品質低下が問題となった。トマトでは従来通りの栽培が困難になるなど、深刻な影響が出ている。このような状況を背景に、バイオスティミュラントへの関心が高まっている。
2018年2月、肥料メーカーを中心とする8社が「日本バイオスティミュラント協議会」を設立した。その後、肥料業界だけでなく農薬業界からも参入が相次いでいる。
ファイトクロームは、2024年3月に関連メーカーと農業資材販売会社と連携して「環境ストレス研究会」を立ち上げ、現地実証に取り組んだ。また、アリスタライフサイエンスとサカタのタネの協業も発表された。
こうした中で、会員企業の間で関心が高まっているのが、BSの位置づけである。効果を科学的に証明しにくい点が課題となっているため、協議会は農林水産省と指針について議論を重ねている。協議会内の組織である技術調査委員会では、BSの自主基準について検討を進めている。具体的には、「安全性」「品質」「効果・効能」の基準を設けることや、農薬登録のない「農薬疑義資材」(農薬登録を受けずに農作物への使用が推奨されるもの)とならないよう注意が払われている。SDS(安全データシート)や重金属濃度情報の提示を必須とするほか、効果の表記方法については「ポジティブリスト」を作成して対応する方針である。特に、農薬登録のある植物調節剤と同じ効果をうたう表記は避けなければならない。協議会では、新規加入時にチラシなどの表記をチェックしている。
また、BSの研究開発も進んでいる。農林水産省が発表した「みどりの食料システム戦略」は、化学肥料30%削減、化学農薬の使用量(リスク換算)を50%削減する目標を掲げている。その取り組みとして、病害虫が薬剤抵抗性を獲得しにくい農薬の開発や、BSを活用した革新的作物保護技術の開発が示されている。また、人手不足が急速に進む中、農薬や肥料散布の省力化に役立つドローンの普及が進んでいる。ドローンの欠点ともされる限られたタンク容量、短時間飛行に対応できるよう、高濃度でも散布可能なドローン対応のBSの増加も期待される。
作物の収量ギャップ抑える
改めてBSとは何か。日本バイオスティミュラント協議会(BS協議会)によれば、作物の収穫量は種の段階で遺伝的に最大値が決まっている。しかし、発芽期、苗期、開花期、結実期、収穫直前といった成長過程で、病気や害虫(生物的ストレス)、高温や低温、物理的な被害(非生物的ストレス)を受けると、本来収穫できるはずの量が減少してしまう。この収量の減少分を「収量ギャップ」と呼ぶ。このうち、非生物的ストレスによる収量減少を抑えることが、BSの役割である。
農薬は、害虫や病気、雑草、生長調節といった生物的ストレスへの対策を目的としている。一方で、BSは、干ばつ、高温障害、塩害、冷害、霜害、酸化的ストレス(活性酸素によるダメージ)、物理的障害(雹や風の害)、さらには農薬の薬害など、非生物的ストレスへの耐性を高めることを目指す。この結果、作物の収量増加や品質向上を実現することが期待されている。
BSは、肥料や農薬と異なり、作物本来が持つ成長力を引き出す資材として注目されている。環境ストレスへの耐性を高める効果があるため、持続可能な農業に貢献するとされている。
日本では古くから海藻資材やぼかし肥料などが農業現場で利用されており、これらは非生物的ストレスの緩和に役立つものだった。
BS協議会では、これらの資材を以下の6つのカテゴリーに分類している。①腐植質、有機酸資材(腐植酸、フルボ酸)②海藻および海藻抽出物、多糖類③アミノ酸およびペプチド資材④微量ミネラル、ビタミン⑤微生物資材(トリコデルマ菌、菌根菌、酵母、枯草菌、根粒菌など)⑥その他(動植物由来の機能性成分、微生物代謝物、微生物活性化資材など)。 このようにBSには様々な種類がある。それらは、肥料や土壌改良剤、農薬と組合わせて散布する事が可能だ。なお、現場での課題に応じて、上記の表を参考にできる。
日本BS協議会・和田哲夫氏に聞く 自然界からの贈り物 上手な使い方と考え方
「植物のケアは治療を超える」――バイオスティミュラント(BS)は、環境ストレスへの対抗手段として、植物の成長を支え、農業の未来を切り開く可能性を秘めた資材だ。人類への自然界からの贈り物とも言えるBSを、どのように活用すればその恩恵を最大限に引き出せるのか。本記事では、BSの基本的な使い方、選び方、そしてその可能性について、日本バイオスティミュラント協議会(以下、JBSA)の和田哲夫氏に解説してもらった。【はじめに】BSは大げさに言えば、人類に与えられた自然界からの贈り物とも言える存在です。これを大切に、そして上手に使うことが肝心です。
【バイオスティミュラント(以下、BS)の上手な使い方】
原則としての留意点は次の通り。
▽BSの使用タイミング=BSはストレスが発生する前に使用します。ストレスが発生した後では効果が出にくくなります。そのため、農薬散布と一緒に毎週散布するよう指導されているのはこの理由の一つです。
▽栽培初期からの利用=BSは、播種時や栽培の初期段階からの利用で効果を発揮します。ただし、果樹などでは後半の時期に利用する場合もあります。
▽対応可能なストレス
=BSは、「暑さ」「寒さ」「日照り」「多雨」「干害」「低温」「肥料不足」などの植物にとってのストレス、主に物理的なダメージを軽減する資材です。これらは一般に環境ストレスと呼ばれます。
効果が出やすいのは、植物が枯れない程度のストレスで、BSの力で回復が可能なレベルのものです。
▽効果の範囲=効果は収量で見て15%~30%程度、ストレス被害にあったケースより高くなることが一般的です。ただし例外もあります。
▽ストレスが少ない場合の影響=ストレスがない年や、ストレスが小さいシーズンには効果の差がほとんど見られない場合もあります。BSの効果が分かりにくいのはこのためです。
【どのようなBSを使うべきか?】
BSには多様な種類があり、1つの製品が複数のストレス軽減効果を示すことがあります。そのため、1つのストレスに対して複数のBSが推奨されます。表1は簡易的な早見表です。
【バイオスティミュラントの実態】
BSは決して新しい製品群ではありません。これまでも肥料や資材として販売されていた製品が多いのです。
2022年にヨーロッパの法律(FPR法)で定義と分類が規定されたため、日本でもこれに追随する動きが始まりました。現在、農水省とJBSAの間でBSの定義、ガイドライン、表示方法について意見交換が行われており、今後の動向が注目されています。
現時点では、各国ともBSを肥料でも農薬でもない新しい製品群として位置付けています。
【ヨーロッパのガイドラインの概要】
EUでは、新肥料法(FPR法)以前は加盟各国ごとの肥料法が存在していました。FPR法で登録がなくても、これまで販売されていたBSは継続販売可能です。そのため、各社はCEマーク(EU全体で販売可能なマーク)の取得を急いでいない状況です。
たとえば、これまでの肥料法では微生物を含む肥料が許可されている一方で、FPR法では窒素固定菌や菌根菌以外の微生物系BSはカバーされていません。このため、微生物系BSは各国の肥料法で販売を続ける必要があります。
EUの方針は、①BSを肥料法のカテゴリーに含め、透明性を向上させる②BSによる肥料効率向上で、肥料輸入量削減を目指す③化学農薬の登録失効が進む中、それに代わる植物活性化効果に期待する、となっています。
EUにおけるBSの効果は、栄養物質の効果的利用の促進、非生物的ストレスの緩和、品質向上、固定化された土壌中の栄養成分の放出促進などの作用をもたらす、とされています。これらは収量向上だけを目的とするものではありません。
EUで挙げられるBSの例として、海藻、植物抽出物、Rhizobium、Azospirillum、Azotobacter、Bacillus、Mycorrhiza、フミン酸、アミノ酸、ペプチド、シリカなどがあります。
【BSの理論的裏付け】 ベルギー・リエージュ大学のジャルダン教授は、BSの理論的基盤について以下のように説明しています。
①エピジェネティクス(Epigenetics)=植物細胞には記憶があり、遺伝子配列を変えずに制御する機能があります。②プライミング(Priming)=植物は悪条件を受けることで、それらに備える能力を持ちます。③ホロバイオント(Holobiont)=植物は微生物群と相互作用し、環境に対処します。④バイオスティミュラント(Biostimulants)=植物に処理された微生物や物質が、遺伝子発現を調節し、エピジェネティック効果をもたらします。
「Plant care is more than plant cure...」。植物の世話(ケア)は、植物の治療(キュア)を超えたものである、という考え方が重要です。病害虫防除は植物の維持管理の一部に過ぎないのです。
【最後に】
昨年、私がブラジルで見聞したところでは、ブラジルにおけるBSと生物農薬の市場は、1000億円以上となっており、その理由としては、野外の大豆、コーンなどの大作物に使用されているからであることが分かりました。その理由は、大型のブームスプレイヤーに取り付けた播種機で播種した直後に小型のタンクに入った液体のBSをその植穴に噴霧するという効率のいい処理方法が利用拡大の鍵のようです。
ハイポネックス アミノ酸・海藻・菌根菌 様々な活用方法を提案

ハイポネックスジャパン農芸プロダクツ部は、バイオスティミュラント資材についての試験を各地、各作物で推進している。同社は、2017年に90カ国以上にBS製品を輸出しているスペインのキミテック社と業務提携し、日本の作物や栽培形態に合わせた菌根菌資材の「マイコジェル」や、アミノ酸とフルボ酸を含む「ボンバルディア」、アミノ酸の「ライゾー」、フルボ酸の「バタヨン」など様々なBS製品を国内で展開している。
「マイコジェル」は、菌根菌資材で、生育初期に根に菌根菌を感染させ、菌糸を伸ばし約2週間で菌根圏を形成する。この菌根圏は株を丈夫にして病気への抵抗性を高めるほか、養水分の吸収効率、干ばつや塩害などのストレス環境下での耐性を高める。
例えば水稲では、浸漬の工程で「マイコジェル」を処理して菌根菌を付着させる方法を提案(試験レベル)している。
初期に発芽し、伸長してくる根に菌根菌を感染することで、土壌中に伸びていく根による養水分吸収や土壌内での微生物抵抗性を菌根菌の菌糸の伸長、増殖効果によって増強する。野菜などに比べて、水を張る水田では効果があまり出ないケースもあるが、干ばつで水が少ない状況や、移植後の根張り促進などに役立つと期待されている。
また、アミノ酸を含む「ライゾー」は、2次根、3次根の発達に効果的でリン酸やカリの吸収に重要な細根を増やし「マイコジェル」と組み合わせると相乗効果が期待できる。「ライゾー」は、植物成長ホルモンのオーキシンや細胞成長因子のポリアミンの生成に役立ち、2次根、3次根の発達に役立つ。例えば、育苗時に「あと5日で田植えしないといけないが根張りが悪い」といった場合に「ライゾー」を施用し通常のプール育苗をしたところ、新しい白根や毛細根の発達が非常に良くなるといった事例もあった。
またアミノ酸とフルボ酸を含む液肥の「ボンバルディア」も主力製品の一つ。15種のアミノ酸を高濃度で含み、細胞分裂や代謝、ストレス耐性を促進。植物性100%でアミノ酸を有効利用しやすい。
また、今年は夏の高温対策として、海藻系の「シーウェックス」を発売した。海藻類と微細藻類を主成分とする同社初の海藻系BSで、ミネラルの吸収を助けたり、土壌の団粒構造を形成して保水性を改善するアルギン酸や細胞の水分保持能力を向上させるマンニトールが含まれる。また浸透圧を調整し、水分や熱ストレスから植物を保護するベタインや、ストレス反応を改善するポリアミンも含む。これらの成分が夏の干ばつや高温耐性を高めてくれる。
来年1月には、菌根菌を活性化させる「マイコエナジ―」も発売。植物由来の新規有効成分で、圃場に生息する菌根菌を全体的に活性化させ、共生率を向上、養水分の吸収を高める。菌根菌資材と併用することも可能。
日本で原料販売加速 ボレ ガード独自の高機能フミン酸
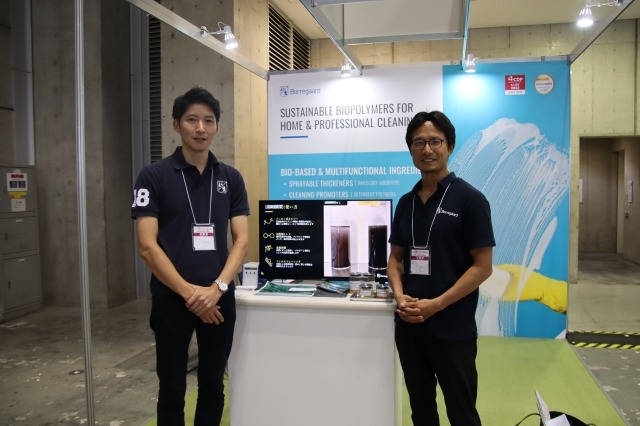
日本支店の代表・中川氏(左)と武川氏
ノルウェーに本社を置くボレガード日本支店は、土壌改良に最適な高機能フミン酸として「ボレグロHA―1」を日本市場で原料販売している。海外では既に17カ国で展開している。
最大の特長は広範囲pHにおける溶解度が高いため、日本の酸性土壌(pH3以上)でもフミン酸の効果を発揮できる点だ。日本は酸性土壌が多い。同社によると、一般的なフミン酸はpH8以上のアルカリ性領域の土壌でなければ溶解しにくいのに対し、「ボレグロHA―1」は、独自の製造技術によって高い溶解度を実現しており、日本の酸性圃場でも有効だという。
さらに、1㎏/10aという少量で効果を発揮できるため、大量投入の必要がなく、省コスト、省力化にも寄与する。
フルーツ山梨農業協同組合(JAフルーツ山梨)は今年、シャインマスカットの圃場で「ボレグロHA―1」の圃場テストを開始。国内外で高い評価を受けるシャインマスカットは、苗木から丹念に育てられているが、毎年の収穫高を維持する一方、圃場の土壌劣化が懸念されている。化成肥料の多用は、生物多様性の減少や持続的な収量の低下を招く長期的な課題となっている。こうした背景のもと、「ボレグロHA―1」が注目された。今後数年をかけて実証試験を進めていく予定だ。
同社日本支店代表の中川氏は、「ボレグロHA―1は、化成肥料の使用量低減と堆肥資源の原料枯渇リスクの回避ができる。土壌改良の腐植質として代表的な堆肥は、近年ではエネルギー資源として需要が高まっており、今後安定供給が難しくなる可能性がある。そこで、少量で効果を発揮し、安定的に入手可能な原料として提案している」と述べている。
※ボレガード社は針葉樹を主原料としたリグニンやセルロース製品のリーディングカンパニー。日本でも複数の産業でビジネスを展開している。


.JPG)





