「ZERO」から「変革」をレベルアップ 〝次の100年〟に向けて 24年ヰセキ全国表彰大会

目次
〝次の100年〟に向けて 24年ヰセキ全国表彰大会
〝次の100年〟に向けて 24年ヰセキ全国表彰大会

始めに冨安社長が挨拶。冒頭、能登半島地震についてお見舞いの言葉を述べ、続いて受賞者やそれを支えた職場のメンバーや家族の尽力に敬意と謝意を表した。その後、中長期的な市場環境、それを踏まえた2024年の取組み、昨年11月に立ち上げた『プロジェクトZ』と来年の創立100周年に向けての意気込みなどを語った(別掲)。
その後、石本徳秋営業本部長が営業方針とイチオシ商品を熱く説明(別掲)。その後、「昨年、私にとって最も嬉しかったニュースは、WBCでJAPANが世界一になった事、そして、大谷翔平選手がドジャースに移籍し、青いユニフォームに袖を通すことになったことです。その会見の中で、『勝つことが僕にとっていま一番大事なこと』と発言され、大いに共感しました。私たちヰセキグループもどんなに厳しい戦いであれ、青いつなぎに身を包み『勝つこと』にこだわり戦い抜いて、とにかく『売り』を伸ばして行きたいと思います。営業は勝てば官軍です」と気炎を上げた。
次に、渡部勉開発製造本部長が最適な生産体制の構築と開発製造本部方針を説明(別掲)。また谷一哉海外営業本部長が「個と組織のレジリエンスを高め、中期最終年度目標の仕上げと次のステージへの具体策を確立する年とする」などと今年の基本方針を説明した(別掲)。
続いて、エクセレントサービスマンクラブ(ESC)245名、スーパールートセールスマンクラブ(SRC)6名が会員認定。縄田常務が登壇者1人1人を出迎え、石本営業本部長から代表者に認定証が贈呈された。
続いて、エクセレント・セールス賞表彰。今回はフランスからヰセキフランス社のフィリップ・ティエール社長など12名が来日。壇上で紹介された。冨安社長は「井関農機は2022年から2023年の2年連続で1億ユーロ(約160億円)を超える売上高を達成したヰセキフランス社の優れた営業実績に深く感謝申し上げます。また2023年において井関の販売会社の中でトップの営業利益を達成されたことを讃え熱く賞賛します」と述べ賞状を授与、谷本部長が記念品を贈呈した。
ティエール社長も日本語で挨拶。「非常に光栄です。今後さらに困難な数年間になると思われますが、私達は最善を尽くし、乗り越える努力を致します。今後も、ご期待に応えられる業績を上げて参りたいと思います」と述べた。
休憩をはさみトラクタ拡販賞(31名)、チャレンジ賞(175名)が、続いて、スーパーセールスマンクラブ(SSC)152名に認定証が石本営業本部長から贈呈された。
その後、整列したSSCダイヤモンド会員から1名がセンターに歩み出て、決意表明。「井関農機の全社員を代表して、決意を申し上げます。本日は冨安社長様を始め、石本・渡部・谷本部長様の力強い決意のお言葉を賜り、改めて心が引き締まる思いです。農業を取り巻く環境はスマート農業の普及拡大、農地集約に伴う大規模化・作物転換など大きく変化しています。また、世界においては戦争や紛争による肥料生産と輸出等に混乱が生じ、我が国も『食料安全保障』という大きな問題が顕在化しました。今後、世界人口は100億人に達すると想定されており、食料増産は喫緊の課題となっております。そのような中、我々ヰセキグループ社員一同は、農機のプロとして、今後もお客様に有益な提案をし続けることで農家の皆様をサポートし、グループの発展に邁進するとともに、農業の持続的な発展に貢献していく所存です。来年には『ヰセキ創立100周年』という大きな節目を迎えます。この節目の年をグループ社員全員で明るく迎えられるよう、グループ方針を全社員の強固な意志とし、2024年の事業計画完全達成をここに誓い、決意表明と致します」と読み上げ、決意書を石本営業本部長に。石本本部長が「力強い決意表明頂きました!共に頑張っていきましょう!」とそれに応えた。
その後、特約店表彰及び販売会社表彰。冨安社長から表彰状が、石本営業本部長からトロフィーが手渡された。販売会社表彰は最優秀賞にヰセキ東北、優秀賞にヰセキ関東甲信越、敢闘賞に三重ヰセキ販売。
引き続き三重ヰセキ販売の松田社長が令和5年秋の叙勲で旭日双光章を受章された旨が紹介。松田社長は「このような栄誉に浴すことができたのも三重ヰセキ販売の社員と井関グループの皆様のお力添えの賜物と大変有難く思っております」と感謝の意を示した。
「プロジェクトZ」のリーダーを務めていく小田切元代表取締役専務の閉会挨拶が棹尾を飾った(別掲)。
冨安社長の挨拶 中計の基本戦略完遂 ベストソリューションの提供
【中長期的な市場環境】
ウクライナ侵攻を経て顕在化した食料安全保障が社会課題として浮き彫りとなりました。国内では食料自給率の課題を抱え、現在80億人の世界人口が2050年には100億人に達すると言われており、食料の増産ニーズは世界的なテーマとなっています。また、国内外を問わずSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた取り組みが求められています。
そのような中で、国内市場は、大規模化、先端技術活用、畑作への作付転換といった大きな変革期にあります。現在改正が予定されている「農業基本法」では、食料安全保障の観点から食料自給率の向上や、気候変動等の環境負荷への対策が求められると想定され、農機メーカーである当社の果たす役割は大変大きなものと考えております。
海外市場では、農業機械の普及が進みつつあるアジアで成長していく必要があります。また欧州では電動乗用芝刈機を限定販売していますが、環境に配慮した商品のニーズが益々高まっています。
【2024年度の取り組み】
私たちがすべきことは、中期経営計画で掲げた基本戦略を完遂することですが、本日は「ベストソリューションの提供」に絞ってお話します。
【ベストソリューションの提供】
国内においては、農業の大規模化・スマート化に加え、農政が進めている「みどりの食料システム戦略」にみられる環境保全型農業の取り組みを加速させていきます。大規模化・スマート化については、快適性やスマート・安全機能を拡充したトラクタBFシリーズを昨年発売した他、田植機では、リアルタイム可変施肥田植機に、マップデータ連動型を新たに設定しました。また「アイガモロボ」を活用した有機農業の拡大と共に環境保全型スマート農業を推進していきます。
今後も、様々なお客さまのニーズにお応えし、国内市場で戦うための商材と体制を整えてまいります。皆様にも引続き、提案力・サポート力のさらなるレベルアップをお願いいたします。生産者の「夢ある農業」「儲かる農業」を実現する「食と農と大地」のソリューションカンパニーとして、皆さまには、更なるご奮闘を。一緒に今期商戦を戦っていきましょう。
一方、当社グループの海外事業は、農業と非農業の分野に大別されますが、中期経営計画よりも先行して伸びています。農業分野については、アジアでの農業の生産性向上を、非農業分野では欧米を中心に生活の質の向上を当社の重点テーマとしています。そのうちアジアでは、インドTAFE社との技術・業務提携を一層推進していくとともに、タイでは販売網の拡充に加え、インド製の小型トラクタなど畑作向けの拡販・他地域展開も含め本格的な成長を目指します。非農業分野については、欧州においてISEKIブランドの景観整備用トラクタや乗用芝刈機などを提供しております。さらには、欧州の高い環境意識に対応した電動芝刈機の限定販売を開始しております。ニーズを的確につかみ、本格販売に繋げていくと共に、更なる電動化商品の拡充に取り組んでいきます。また、北米では、AGCO社との協業を一層深化させ、販売量とシェアの拡大を目指します。
それぞれの地域に応じた商品戦略や販売・サービスの強化を通じ、市場での存在感アップとブランド拡大に繋げ、海外事業の次のステージへの具体策を確立して参ります。
【「プロジェクトZ」について】
昨年11月に立ち上げた「プロジェクトZ」は、開発・生産・販売の各分野でそれぞれのやり方や社内体制をゼロから見直し、強靭な経営基盤を構築することを目的として始動しました。具体的な方針については今後打ち出していきますが、開発・生産・販売の各現場を巻き込んだ「変革」を進めていきます。プロジェクト名の「Z」は、アルファベットの最後の文字ということから無限・未知を表し、そこから未来へのチャレンジ、「全てをZEROから見直す」という思いを込めています。本プロジェクトを中核として、グループ一丸となり「変革」を実行していきましょう。
結びとなりますが、本年は、いよいよ100周年に向けたカウントダウンが始まります。100周年に向けて記念ラベルを製作し、本年から記念機への貼付けなど皆さまの目にも触れることとなります。ラベルのデザインに込められた思いは、「結びつき」と「無限の持続性」です。来年の創立100周年、そして次の100年に向けて、一人ひとりが「プロジェクトZ」の担い手として、本年をZEROから「変革」をレベルアップする年にしていきましょう。
石本営業本部長の挨拶 勝ちにこだわり前進 3月価格改定、全力推進を
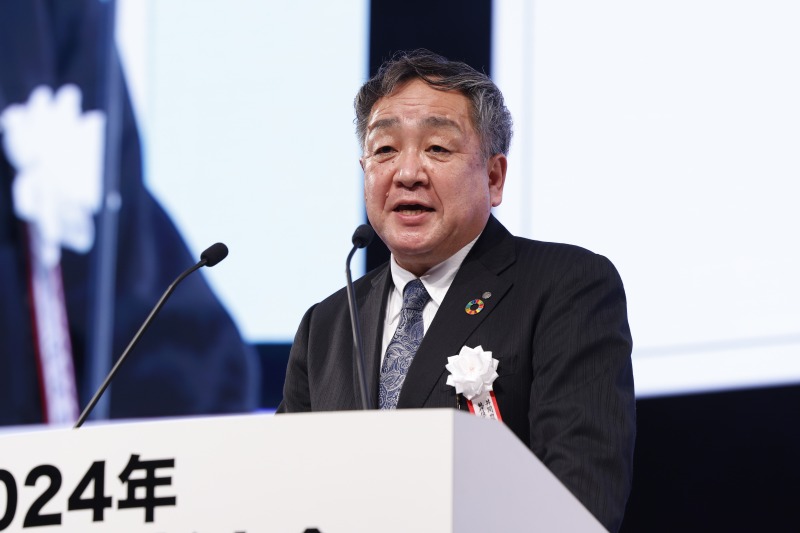
本年度の営業方針を申しあげます。まず、2024年3月には、井関製品の価格改定を実施させて頂きます。原材料価格、運送費の高騰は著しく、その影響の全てをカバー出来ていないことから、3年連続3回目の価格改定となります。価格改定前の推進にとれる時間は限られますが、2月まで全力推進をお願いします。
さて、今年の営業の一押し商品です。まずは、昨年発表されたBFトラクタ。細かい説明は抜きで、体感してもらって下さい。本年も全国各地で継続開催するISEKIアグリジャパンフェスタも活用し、とにかくMSNです。続きまして、肥料高騰対策・今後の事業獲得には必須。マップデータを使用して可変施肥ができるザルビオ対応可変施肥田植機PRJ―FS仕様、そして井関しかないリアルタイムセンシング可変施肥田植機と、共にスマート農機として積極推進願います。
また、大好評の直進アシスト機については直進アシストが提案できる商品が出揃いました。2024年はTPHともに直進・直進・直進で計画達成に向かって真っ直ぐに突き進みましょう。
更に、農政が掲げる「みどりの食料システム戦略」に関連。アイガモロボでは、有機農業に取組む農家の皆様を中心に好評です。また、生産者と共同でカーボンクレジットを生成し、クレジット取引を手助けすることで脱炭素農業を推進する取り組みも展開します。最後にコンバインですが、全農共同購入機第3弾は他社で決定され、当社としてもこれに対抗する本格4条ベースのコンバインを3月に出荷開始します。市場の動きは低価格機同士での商戦となりますが、勝つ営業展開で推進願います。また、担い手層向け4条・5条刈りフロンティアFMも自信をもって薦めてまいります。
当社は来年100周年を迎えます。プロジェクトZでの営業部門は販売・サービスと『ゼロからの見直し』変革を進めてまいります。
今年は中期経営計画達成に向けた最終コーナーを駆け抜ける年であるとともに、100周年に向けて助走の年となります。「勝つこと」にこだわり前進してまいりましょう。
小田切専務の挨拶 全社でプロジェクトZ 〝提供しつづけていく〟ために

各地での熾烈な商戦を逞しく勝ち抜き輝かしい成績をあげられた皆様、受賞、誠におめでとうございます。
昨年は緊張が増す世界情勢の中で経済活動全てが影響を受けました。また農家様には、異常気象、生産資材価格高騰が大きな影響を及ぼしました。そのような中で、食料安全保障の重要性の観点からも農業への注目が高まっています。私達は農家のため、社会のために今後も益々重要な役割を果たしていかねばなりません。〝お客様に喜ばれる製品〟を提供し続けることが一番大事です。それはお客様の困り事をしっかり解決し、信頼関係を結ぶところから始まります。そのように信頼関係を築き上げたてきたことが受賞者の皆様の力の源であると確信しています。
一方で〝提供し続けていく〟ためには、持続的な成長が必要ですが、それは従来の延長線上では語れなくなっています。この変化に適切に対応すべく我々は数々の「変革」に取り組んで参りましたが、いま、より一層の速さと深さが必要となっています。そこで弊社では昨年11月に、強靭な経営基盤を構築することを目的に「プロジェクトZ」を発足させました。来年、創立100周年を迎え、次の100年に向け開発・生産・営業のあらゆる活動の帆を大きく張り、勇気を持って舵を切っていくプロジェクトです。
本年の干支は甲辰(きのえたつ)。「成功という芽が成長していき、姿を整えていく」年と言われており、まさに当社と「プロジェクトZ」を啓示しているように感じます。
プロジェクト発足の準備をする中で、既にいくつかのアイデアについて検討、議論を繰り返してきたところですが、今後、徐々にその取り組みが明らかとなり、各職場の第一線をも巻き込んだ活動になってきます。
「プロジェクトZ」は全社的な取り組みです。全員がプロジェクトのメンバーとなって、龍の如く猛々しく、新しいことに挑戦する年にして参りましょう。今年も〝勝ち〟に拘り目標達成、よろしくお願いします。
谷海外営業本部長の挨拶 しなやかに強靭に 海外事業を次のステージへ
井関グループの海外事業は、中計3年目に当たる昨年、北米では金融政策の変更等によりコンパクトトラクタ市場が調整局面に入り、一方で円安や底堅い需要が支える欧州事業が好調を持続し、海外事業全体では3期連続で過去最高の売上高となりました。また事業収益性も、地域別に濃淡はあるというものの中期計画以上の改善が図れました。
このように、現中期計画対比では順調ともいえる当社海外事業ですが、当社の海外売上高比率は未だ30%台です。当社の技術力・総合力を考えれば、更なる「伸びしろ」がある事は明白です。
具体的に地域別で申し上げれば、まず、北米。昨年、北米市場は調整局面に入ったとはいえ、50馬力以下の市場台数は17万台と日本国内の5倍以上の巨大なマーケットです。ここでは、戦略パートナーのAGCO社を通じて、シェアアップ、量の確保に努めていきます。領域を絞り、地域特性を考慮した製品投入や現地でのカスタマイズ、またその領域で強みを発揮する販売小売店数の増もAGCO社と共同で検討を進めていきます。
欧州においては、ISEKIブランドが既に浸透しています。特に景観整備市場は、フランスのISEKI France S.A.S、ドイツのISEKI Machinery G.m.b.Hの販売網は業界トップクラスですので、その販売網を通じ「持続可能な街づくり」に貢献できる自社、また他社による商材の拡充に努めます。特に環境問題にセンシティブな欧州では電動商品にその期待がかかっています。また欧州の更なる販売網強化には、非オーガニックな手法であるM&Aなども鋭意検討して参ります。
アジアは3つに分けて説明させていただきます。1つは日本国内で培った水稲用農機、特にプロ用の商材の輸出、農業構造が似ている韓国や台湾への輸出です。韓国はここ5年間の平均で日本国内の総台数に近いHJコンバインが販売されており、今後は直進アシスト等の高付加価値製品の導入にも大いに期待がもてます。
2つ目はアセアンです。2021年から完全子会社化したIST社ですが、2年連続の黒字という順調なスタートがきれたものの、昨年は大苦戦でした。
背景には気候変動に端を発した環境の変化がありますが、これは単年ではなく、今後も続くタイ農機市場の構造変化とも捉えています。そこで安定した事業拡大を進めるためにも、個人向けの稲作農家ばかりではなく、キャッサバやサトウキビを生産する畑作、また製糖工場などの法人向け営業に努め、市場変化に早く適応させていきます。
3つ目はインドです。我々のパートナーとなるTAFE社はインドで2番目の農機メーカーですが、これまでは当社の知財譲渡による収益化を行ってきました。また昨年はTAFE社が設計・生産したトラクターを、タイのISTに輸出し販売する試みも開始しました。
今後は同社のコスト競争力の高い部品やコンポーネントを当社製品にも活用すると共に、共同で開発、生産する商材を世界各国で販売していく検討なども進めています。この数年とは異なり、欧米のインフレによる購買力停滞など事業環境の先行きは不透明さを増しています。
しかしながら我々には過去に好事例も多く、本日お招きしているISEKI France社の前身である会社は、2013年には絶望的な有利子負債を抱え、売上高も現在の半分でした。ところが子会社化後には、ティエール社長の力強いリーダーシップのもと、大幅な事業拡大を成功させ本日の表彰に繋がっています。Impossible n’est pas français.不可能という言葉はフランス語ではない、つまりフランスは何でもできる、という力強い言葉です。
私はこれまでの経験を基にImpossible n’est pas ISEKI、我々井関ならば、如何なる困難も乗り越えられる、このように固く信じております。そのためにも海外営業本部では、益々個人のスキルアップや組織の強化を図って、更に個と組織のレジリエンス、即ちしなやかな強靭性を高めながら、海外事業の次ステージへしっかり向かって参ります。
渡部開発製造本部長の挨拶 筋肉質な生産体制へ 大規模・スマート・環境

私は、井関農機に入社以来40年、開発製造本部で開発をメインに携わってきました。この間には、現場は違えど、ヰセキ製品として世に出すモノをより良くするために、との同じ思いで営業現場の方々からの多くのお声やお知恵を頂き、開発に反映させてきました。
我々は、開発・生産現場で開発者や作業者が思いを込め、試行錯誤のうえ生みだした製品を、大切に、誠意をもってお客様のもとへ〝1台でも多く〟の思いで営業頂いておりますことに、改めて厚く御礼申し上げます。
さて、本年も厳しい事業環境が続くことが予想されます。より一層の速さと深さを兼ね備えた「変革」が必要となっております。
国内製造所では最適な生産体制の構築を進め、「売上高に左右されることなく収益を上げられる筋肉質への体質転換」に向け、取り組んでいます。
開発においては、中計施策の軸である農業の大規模化・スマート化に加え、農政が進めている「みどりの食料システム戦略」にみられる環境保全型農業の取り組みを加速させていきます。
大規模化・スマート化については、既にトラクタ・コンバイン・田植機すべてに直進アシスト機能を搭載しており、昨年6月に発売したトラクタBFシリーズには無段変速トランスミッションの搭載に加え、快適性能・スマート・安全機能を拡充し、農業の生産性向上を目指しております。田植機では、業界に先駆け、リアルタイム可変施肥田植機を開発しました。これに加えて、全農が推奨する「ザルビオフィールドマネージャー」を活用したマップデータ連動型可変施肥田植機を新たに設定し、施肥量の低減により、肥料価格高騰に対するソリューションに繋げていきます。
更に、私たちには農業機械メーカーISEKIの企業の一員として、社会課題の解決に取り組む必要があり、国内外を問わずSDGsの達成に向けた取り組みが求められています。
ヰセキグループの長期ビジョンに掲げる「食と農と大地のソリューションカンパニー」としての役割を果たすため、食料安全保障の観点から食料自給率の向上や、気候変動等の環境負荷に配慮した対策への取組みを一層強化する必要があります。
私達は現下の厳しい事業環境の変化への対応と企業価値向上を図るために、開発・生産・営業の各現場でそれぞれが奮闘を重ね、前例踏襲から脱却を図り、戦い抜かなければなりません。
2024年度、開発製造本部では「誰もが欲しがり、世界中で儲ける商品を創造する」と本部方針を定めました。基本に立ち返り「全ての出発点はお客さま」を念頭に、確かな「品質」で「コストパフォーマンス」に優れた製品を「タイムリーに」皆様にお届けし、自信をもって営業いただけるよう、精一杯、開発製造本部一丸となり、取り組んで参ります。











