「BSC工法」を説明 日本工営、東京農大、日健総本社 土壌藻類を活用した新技術
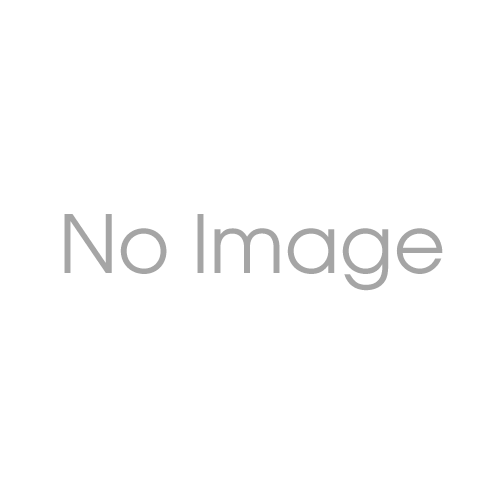
日本工営=新屋浩明社長、東京都千代田区麹町5―4=は2月3日、包括協定を締結している日健総本社=森伸夫社長、岐阜県羽島市福寿町浅平1―32=と東京農業大学によるBSC工法の試験法面を報道陣に公開し、併せてBSC工法の最新情報や研究内容の紹介を行った。同社と日健総本社および東京農業大学は、2022年2月に締結した包括連携協定のもと、農林水産物を軸とした開発技術等を用いた地域活性化において協力の推進と発展させることを目的に取り組んできた。

日本工営の新屋社長
BSC工法は、土壌藻類を活用した表面浸食防止工法だ。土壌藻類資材を散布してBSC(糸状菌類、土壌藻類、地衣類および海苔などが地表面の土粒子や土塊を絡めて形成するシート状の土壌微生物のコロニーのこと)を形成し、浸食を防止して早く植生遷移をスタートさせる工法。造成法面、崩壊・工事による荒地にも適用できる環境に配慮した画期的な技術だ。
日本工営が開発した土壌藻類により土壌流失防止および土壌飛散を防止するBSC工法、日健総本社が開発した糸状藻類活用を基に、東京農業大学の総合農学における知見との融合による新技術開発、新規機能性素材の開発、さらに農林水産物を軸とした開発技術等を用いた地域活性化における協力を推進・発展させることを目的に取り組んでいる。
説明会の冒頭、挨拶で江口学長は「BSC工法は地球環境の色々なところにあるものを使っており、生態系を乱すことがないということが大きなポイント。ドローンなどで散布できれば、より地球環境保全に繋げられるのではないか。この工法は大きな可能性を秘めている」と期待を寄せた。
次に日本工営の新屋社長が「法面には人工的なものから自然斜面など色々あるが、BSC工法はその法面が崩壊したり剥がれたときに、山そのものがもつ植生の回復力を活用し、生態系を乱さずに、より早く回復させることができる技術だ。それが従来の自然促進工よりも安価で実施でき、環境にも優しい。我々は、この工法が世界中に広がることで、SDGsにも繋がると考えており、今後も一生懸命研究していく」と意気込みを見せた。最後に、日健総本社の森社長が挨拶した。
その後、同社沖縄支店の冨坂技術部長がBSC工法について詳しく説明し、東京農業大学の矢部和弘教授が「全国に広がる東京農大のフィールドを活用したBSC工法の現地適用実験」をテーマに話した。

日本工営の新屋社長
BSC工法は、土壌藻類を活用した表面浸食防止工法だ。土壌藻類資材を散布してBSC(糸状菌類、土壌藻類、地衣類および海苔などが地表面の土粒子や土塊を絡めて形成するシート状の土壌微生物のコロニーのこと)を形成し、浸食を防止して早く植生遷移をスタートさせる工法。造成法面、崩壊・工事による荒地にも適用できる環境に配慮した画期的な技術だ。
日本工営が開発した土壌藻類により土壌流失防止および土壌飛散を防止するBSC工法、日健総本社が開発した糸状藻類活用を基に、東京農業大学の総合農学における知見との融合による新技術開発、新規機能性素材の開発、さらに農林水産物を軸とした開発技術等を用いた地域活性化における協力を推進・発展させることを目的に取り組んでいる。
説明会の冒頭、挨拶で江口学長は「BSC工法は地球環境の色々なところにあるものを使っており、生態系を乱すことがないということが大きなポイント。ドローンなどで散布できれば、より地球環境保全に繋げられるのではないか。この工法は大きな可能性を秘めている」と期待を寄せた。
次に日本工営の新屋社長が「法面には人工的なものから自然斜面など色々あるが、BSC工法はその法面が崩壊したり剥がれたときに、山そのものがもつ植生の回復力を活用し、生態系を乱さずに、より早く回復させることができる技術だ。それが従来の自然促進工よりも安価で実施でき、環境にも優しい。我々は、この工法が世界中に広がることで、SDGsにも繋がると考えており、今後も一生懸命研究していく」と意気込みを見せた。最後に、日健総本社の森社長が挨拶した。
その後、同社沖縄支店の冨坂技術部長がBSC工法について詳しく説明し、東京農業大学の矢部和弘教授が「全国に広がる東京農大のフィールドを活用したBSC工法の現地適用実験」をテーマに話した。







