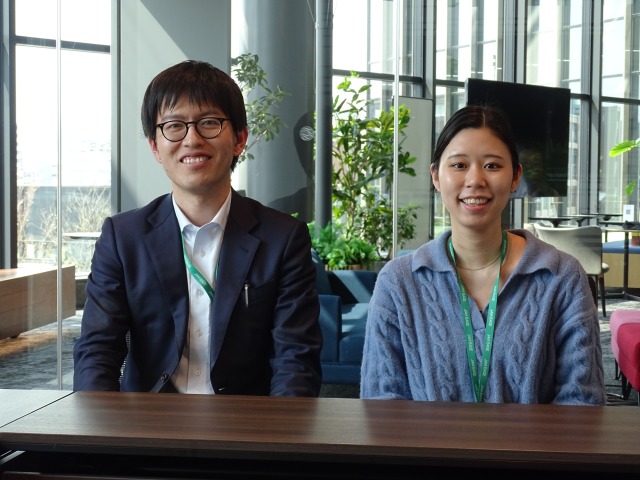クボタが挑む営農型太陽光発電 農業振興と脱炭素 発電と営農で放棄地再生

2012年に再生エネルギーを固定価格で買い取るFIT制度が始まり、翌年には農水省が農地転用上の見解を示し、営農型太陽光発電が制度上可能となった。当初は36円/kWhが20年間保証され、生産者の副収入となったが、年々売電価格は下落し、現在新規参入で採算を確保することは難しい。温暖化が進展する中、再エネ普及にとっては逆風の形。その状況下、クボタは、新たに営農型太陽光発電の取り組みを開始した。なぜ今、この事業に乗り出したのか。取り組みの実際を聞いた。
取り組みのキーワードとなるのは環境、地域、農業、事業の〝持続性〟。温暖化の加速が生産環境を悪化させ、生産現場では農業従事者の高齢化が止まらない。既存の世界が揺らぐ中で明日へと繋がる仕組みづくりが始まっている。
クボタは昨年7月から栃木県周辺でプロジェクトを開始。耕作放棄地を含む農地を活用した営農型の太陽光発電所を順次稼働させている。現在ソーラーパネルの下では麦が栽培され、上部で発電された電気はクボタ筑波工場へと売電(供給)されている。
営農を手がけているのは地権者から農地を委託されて農業生産を行う㈱アグロエコロジーで、発電を手がけるのはクボタ。「私たちが担う役割は、発電設備への投資と発電所の保有です。そして電力の供給を行います。また売電収入の一部を農業法人に還元し当該法人の経営支援にも貢献します」と、プロジェクトを主導するクボタ機械事業本部イノベーションセンターの谷直人さんが教えてくれた。同氏が所属するカーボンニュートラルビジネス企画室の川満璃子さんも加わって頂き、取り組みの現状とこれからについて聞いた。
同プロジェクトは今年の6月ごろを目指して茨城県や栃木県で約50カ所の太陽光発電所を稼働させる予定。合計約20ha、発電容量は5MW。筑波工場で使用する電力のうち約9%を営農型太陽光発電からの再生可能エネルギーで賄う計画で、通常電力に比べてCO2を年間2600t削減できる効果を見込んでいる。
営農を担当するのは栃木県芳賀町のアグロエコロジー。「プロジェクトが始まる以前から営農型太陽光発電に取り組まれ、米・小麦・大豆などの栽培を行ってきた実績があります」と営農面での信頼は厚い。
2023年3月末での、営農型太陽光発電所の設置許可実績(累計)は全国で5351となっているが、栽培されている作物のトップは観賞用植物のサカキ・シキミなどが36%となっており、太陽光発電の場所確保を優先し、営農を本分としていない事業者だと思えるような所も少なくない。その中で本格的な営農を志向する生産組織との連携で地域農業の支援を強く打ち出している。
アグロエコロジーは営農の他、農地の確保や地権者との交渉、クボタから農業委員会への申請手続なども行う一方、営農によって収穫された農産物の売上げを得ることができ、売電収入の一部も副収入になる。
地権者は、10年、あるいは20年という長期の契約を結び、耕作放棄地の解消や、維持のために草刈りなどを行っていた手間から解放され、地代が支払われることになる。「『耕作放棄地の活用に困っていたのでありがたい』という地権者の声も頂いています」。
現在、発電された電力は、クボタの筑波工場へ供給され、三方にメリットがある取り組みとなっているが、採算性は大きな問題。再生エネルギーの現在の買い取り価格では発電事業単体では利益が出ない。取り組みを進めているのは短期的な経済的合理性を超えた力になる。「プロジェクトの起点となるのは第1に農業振興、そして第2に再生可能エネルギー導入による脱炭素化への貢献です」。地域にある耕作放棄地を解消し、また将来的な耕作放棄を未然に防ぎ、地域農業の持続に貢献する。加えて工場が使用する電力を再生可能エネルギーに置き換えることでカーボンニュートラルを実現するために必要となるカーボンクレジットの購入費用削減などに繋げる。クボタの事業基盤となる農業やものづくりを持続する力となる。
この取り組みの大きなポイントとなる農業との両立を図るため、発電設備の随所には工夫がある。標準的なトラクタなどの使用を想定し支柱の間隔は約5m、コンバインなどが利用できるよう、パネル下の最も低い部分でも約3mの高さがある。遮光率は約30%に抑えられ、散乱光も入りやすく、「米、麦、大豆などは、過去の実績からも問題なく栽培できます」。
取り組みの推進については、幾つかの課題もある。自治体ごとに異なる申請要件や許可基準、農地の一時転用による事業継続の不確実性とそれに伴う資金調達の難しさ、営農体制の長期的確保、発電設備と栽培適性の明確化など。改善が進めばより効率的に進む。
今後は全国展開も視野にあり、「将来的には〝地域の資産〟としての営農型太陽光発電になれば」としている。具体的には、設備の建設段階から地域の農家や自治体、金融機関が関与し、発電所の所有も地域と共有するモデルを構想している。発電インフラそのものを地域で支え合う、エネルギーと食の地産地消へと繋がり、地域の脱炭素化を図ることにもなる。
また、長期的展望として、発電所を電動農機の充電ステーションとして活用したり、スマート農業に必要な電力供給拠点としたりするなど、農業の電動化・スマート化との連携も期待される。
営農型太陽光発電はかつてのような利益を追求する事業ではなくなったが環境、地域、農業、事業を持続するためのインフラとしての役割が期待されている。ただそのためにはいくつものハードルがあり、環境価値が十分評価されなければ、取り組みの継続力は弱まる。実感としてひしひし感じる温暖化の進展、農業従事者の高齢化、立ち止まっている時間はないはずだ。全国の生産者や自治体、企業、金融機関などから問い合わせが寄せられているという。地域に寄り添い明日の農業を探る姿があった。